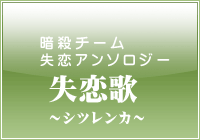思い出になるような「なにか」なんて、ないと思っていた。
Antipasto by ヤミ
さっきまで髪を振り乱して大泣きしていた女はそれでも男が自分の元へと戻らないと分かると、ゴミ袋を取り出して部屋中に散らばった男との思い出を放り込んでいった。目から流れる大粒の涙を拭こうともせず、時々盛大に鼻をすすり、手にするもの一つひとつにありがとうと囁きながら、歯ブラシやスリッパや写真立てやタオルや冷蔵庫に入っていたビールなんかを放り込んでいく。でも心配はない。彼女はこの失恋ののち、所謂運命の人と出会って幸せな人生を送るのだ。二年前に流行った映画。ブラウン管の中の女優は三つ目のゴミ袋を手に取った。
ソルベは隣に座る男に凭れながら興味なさげに映画を見ていた。今夜の酒はイマイチだったが酔いが回るのだけは早く、映画はまだ始まったばかりだというのにすでに瞼が重い。女がぱんぱんに膨れたゴミ袋を部屋から押し出す。もう涙は流していない。ソルベは手に持っていたグラスを置きながらぼんやりと考える。俺もこの男がいなくなったらああやって思い出を捨てるのだろうか。ゴミ袋を持って、部屋を歩き回って。
いよいよ眠たくなってきて、身体をずらし、男の逞しい太ももに頭を置く。男の大きな掌が頭や肩や腰を優しく撫でる。落ちていく意識の中で、ソルベは自分の思考の可笑しさに気づいて笑った。二人の思い出なんて。この男から貰ったものなんて何もないじゃないか。お互いの部屋にも行ったことが無い。二人の間には最初から、捨てるものなんて存在しない。
じゃあ俺はあんな惨めな儀式をしなくてもいいな。いよいよ眠る瞬間に考えたのは、そんな呑気な将来だった。
地下鉄から出て徒歩7分。緑色の看板が掛かったそのバールの扉を開けながら、ソルベは数か月前の自分を思い出していた。二人の間には捨てるのもは何も無いだなんて。思い出は無いだなんて。まさか。
扉を開けると、懐かしいベルの音がする。焼きたてのパンが並んだショーケースからクロワッサンを選び、ルンゴを注文する。あの日、エスプレッソだけを注文した俺の隣りで、男は美味そうにクロワッサンを頬張りながら薄いコーヒーを飲んでいた。
男とはどんな会話をしただろうか。晴れていたか雨だったか。お互いの服装、バリスタとの遣り取り、今までいた場所とこれから向かう場所。一つひとつを丁寧に思い出す。男はクロワッサンを褒めていた。俺は買ったばかりの靴を履いていた。確か青いワンピースを着た女が先客にいて、良く似合っていると声を掛けた男に、相槌を打つ俺。
全部を思い出して、その時の感情まで引っ張り出して、小さくありがとうと呟く。これでまた一つ思い出を処分した。店を出て、深呼吸をする。
二人の思い出を捨てなくてはと気づいたのは、何も無いと思っていた二人にも思い出があったのだと気づいたのと同時で、それらはイタリアどころか世界中に散らばっていた。
お互いに自由だった。いつも男がソルベを呼び出して、その度にソルベは小さな鞄に入るだけの荷物を詰め込んで会いにいった。一晩で別れる時もあったし、六週間も一緒にいた時もあった。その時はアジアの国々を延々とまわっていて、イタリアへ戻って来た時にひどく安心したのを覚えている。
アジアへ行くのにはそれなりの時間が必要だ。当分は仕事が忙しいからこの思い出はまだ暫くは捨てられそうにないな。そんな事を考えながらソルベは歩く。
捨てる作業は意外にもソルベを苦しめなかった。映画の女みたいに大粒の涙を流すことも無いし、惨めだとも思わない。ただ男がいなくなって、無意識に思い出の場所に立っていた自分に気づいた時、それほどに男との時間が自分に染みついていたという事実に恐怖した。それは郊外の小さな本屋だった。あまり読書はしないというソルベに、一冊の本を手に取って好きな作家なんだと教えてくれた。しかし男はそれをソルベに買って寄越すことはしなかった。その時の事を鮮明に思い出したソルベもまた、その棚の前に立ち、同じ本を手に取り、中を開くこともせずに棚に戻す。そうしてありがとうと呟くと、自分の中から小さな何かがコロリと落ちていく気がした。あぁ、俺は今思い出を一つ処分したんだ。そう感じた。
それ以来、ソルベは思い出を捨てながら生きている。
切りピッツァを食べながらローマの街を歩いた。ネアポリスの安い宿で朝を迎えた。スペインの劇場、フランスの屋台、スイスのバス。どんな小さな思い出もその場所に行くと自然と思い出された。数か月、あるいは数年前の記憶が徐々に輪郭を作り、色味を帯び、しっかりとした質量を持って蘇る。そうして隅々までを完璧に作り上げたのち、それらは呆気なく消えていく。残るのは微かな疲労と大きな安堵。そうやってソルベは思い出を捨てていく。
そういえばあの映画を見た宿もこの近所だったな、と思い出しソルベは立ち止まる。予定を変えて宿に寄ってみようか。しばらく考え、しかし当初の予定通り今夜は自分の部屋に帰ることにした。あの緑の看板のバールは密かにお気に入りの店で、その思い出を捨てた今日は普段より少しだけ多く疲れてしまったのだ。
早く帰ろう。
まだ思い出は沢山残っている。けれど映画のように二時間でハッピーエンドを迎えないといけないわけでもない。男と居た頃には吸っていなかった煙草を咥え、ソルベは地下鉄までの道のりをゆっくりと歩き出した。
完