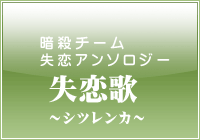あなたの息子はここにいます。愛しています、お母さん。
美しい人 by ヤミ
大砲の上に しゃれこうべが
うつろな目を ひらいていた
しゃれこうべが ラララいうことにゃ
鐘の音も 聞かずに死んだ
+++
「よぉリゾット。今日も盲目バァさんの介護かぁ? 」
朝早くリゾットが出かける準備をしていると、プロシュートが声を掛けてきた。
「介護ではない。任務だ」
コートに袖を通しながら答える。病院行きのバスにはまだ時間がある。
「ハン。介護だろ。毎日毎日汚ねぇ病院に通ってよぉ。死にかけのバァさんの世話するなんて、あ、違う。介護じゃあねぇわな。詐欺だった。結婚詐欺だ、財産目当ての」
ニヤリと笑ってプロシュートが言う。リゾットが眉間に皺を寄せたことには気づいていないようだ。
「詐欺は、否定しない。財産目当てもな。ただ結婚ではない。俺は彼女の息子役だ」
「恋人に成りすますよりタチが悪いと思うがな。でもその仏頂面で“早く元気になってねマンマ”とか囁いているんだよ。傑作だぜ。なぁ、俺も今度同行していいか? 」
プロシュートはいよいよ笑いを抑えることが出来ずに声を出して笑った。
「同行はするな。ボロが出たらどうするんだ。それに俺はそんな事は言わない。俺はただ彼女の話し相手になっているだけだ。もうバスに間に合わないから行くぞ」
リゾットは厚手のマフラーを巻きながらアジトを出た。予定より二十分も早くバス停に着くことになってしまうが、まぁ良い。プロシュートの軽口に付き合うくらいなら寒空の下で凍えながらバスを待った方が何倍もマシだ。吹き付ける風には雪が混ざっている。今夜は積もるのだろうか。
「おはよう、母さん」
病室の扉を開けてベッドに横たわる老女に声を掛ける。サイドテーブルに置いてある朝食はほとんど手が付けられていない。
「ダメじゃないか。ちゃんと食事を摂らなくては」
マフラーとコートを脱ぎながら彼女の様子を確認する。今日はクリーム色のパジャマを着ている。昨日は風呂に入れてもらうと話していたから、その時に着替えたのだろう。顔色は良い。髪にも艶がある。食事を嫌がるのはいつもの事だから、特に心配はない。普段と変わらない様子を見て、リゾットは密かに安堵する。
「だってここの食事は味が無いんだよ。私はもっと味の濃いのが好みだんだ。お前も知っているだろ」
もぞもぞと起き上がりながら彼女は言い訳をする。
「子供じゃないんだから。ほら、食べさせてやるから先にこれを羽織って」
薄紫のガウンを取り出して老女に着せる。これはリゾットが彼女のもとに通うようになってから買ってやったものだ。
「じゃあスープだけおくれよ。今日のはひよこ豆が入っているんだ。でもオレンジはやめておくれ。パサパサで食べられたもんじゃない」
オレンジと言われて、リゾットはトレーに乗せられたままのそれを見た。採れたての新鮮なものだろう。鮮やかなオレンジ色をして、くし形に切られた切り口からは果汁が滴っている。見るからに美味そうだ。
「…とても美味そうなオレンジだが。それに手を付けた様子がないのに、どうしてパサついていると? 」
「フン。匂いでわかるんだよ。オレンジはシチリア産以外はみんなダメさ」
「看護婦にでも産地を聞いたのか。故郷を誇りに思うのは悪い事だとは言わないが、好き嫌いは良くない。さぁ、これも食べてくれ」
スープを飲ませ、オレンジも食べさせた。老女はリゾットが口に運ぶものを素直に咀嚼する。時折まずいとか味が無いとか小さくこぼしながら、でもそれは自分に食べさせてもらう彼女なりの口実だと、リゾットは気づいている。
「そろそろ花を替えなくてはな。次はどんな花がいい? 」
食事の後、リゾットは窓際の花瓶を見ながら聞いた。そこには数日前にリゾットが買ってきた花が半分しおれて入っている。
「花なんていいさ。どうせ見えないんだ。お前の面倒を増やすことはないよ」
彼女はガウンを脱ぎながら答える。どうやらもう一眠りするつもりらしい。
「でも香りで楽しめるだろう。今夜にでも花屋に寄るよ」
「今夜は雪じゃないか」
「どうせ会社には行くんだ。そのまま家に帰るのも花屋に寄ってここに来るのも、大差ない」
横になった彼女に布団をかけてやりながらリゾットは答えた。本当は会社などには行っていないし、雪でバスが止まったらアジトから病院まで歩いてこなければならない。でもそれを億劫だと思う気持ちは一ミリも無かった。
「じゃあもう行ってくる。昼もちゃんと食べてくれよ」
「まずいものじゃなかったら何でも食べるさね」
「美味い食事が出てくることを祈ろう。ではおやすみ」
コートを着て病室を後にする。今日は他の任務は入っていない。本格的な雪が降る前に酒と食料を買っておこうと考えながらバス停に向かった。
+++
「ねぇリーダー。あのターゲットの件だけど…」
「ターゲット? どいつの事だ? 」
アジトに戻るとメローネが声を掛けてきた。メローネには今三つの任務を同時に依頼している。メンバー内で仕事の量が偏るのは好ましくない事だが、彼が得意とする内容の仕事が偶然重なってしまったのだ。無理に他のメンバーに割り振って失敗するよりも、負担は増えるがメローネに全て任せた方が確実だ。
「ほら、リーダーが相手をしている老女のさ、本当の息子だけど…」
メローネは言いにくそうに答える。その態度が少しだけリゾットを苛立たせた。
「潜伏しているアジトが見つかりそうなんだ。シチリアのカターニアまでは分かったよ。来週にでもシチリアに行こうと思う。一週間か…たぶん二週間もあれば探し出して始末出来るはずだ」
シチリアという単語を聞いて、リゾットの表情が険しくなる。
「そうか。では他の任務と調整をしてシチリア行きの予定を立てよう。ただ今回は自然死に見せなくてはいけないからな。ターゲットを殺るときはプロシュートも行かせる」
「わかったよ。でも、あの、もう殺してもいいの? 」
「どういう意味だ? 」
淡々と答えるリゾットに対して、メローネは歯切れ悪く話を続ける。
「だって本物の息子を殺す前にさ、ほら、彼女に遺言を書いてもらわなくちゃいけないんだろ? 自分の財産を息子に譲るって。大丈夫なの? 書いてもらえそう? それに…」
「そのことなら大丈夫だ。彼女との関係は上手く行っている。俺を本当の息子だと信じているし、今夜にでも財産の話をしよう」
「なら良いけど…。でもさ、遺言状を書いてもらうって事は、つまり彼女を…」
「殺すことになるな。今更だろう。俺たちの本業だ。わざわざ話題にする事なのか? 」
普段通りの感情が読めない口調で、しかしこれ以上会話を続けるつもりはないと強く言外に滲ませながら、リゾットはメローネの言葉を遮った。メローネもさすがに何も言えなくなり、他の任務と調整をすると言って部屋に戻っていった。
誰もいなくなったリビングのソファに座り、リゾットは大きくため息をつく。
自分の気持ちなんてメローネに心配されなくてもとっくにわかっているのだ。
彼女の事は既に、単なるターゲットとしては見れなくなっている。
+++
本来ならリゾットの任務は組織に盾突いた男とその仲間の数名を殺すだけのはずだった。逃亡した一味を国内外問わず探し出し、一人残らず始末する。暗殺チームにとっては定番の仕事。しかし男の素性を調べていくうちに、彼には莫大な財産を所有する母親がいることが分った。心臓の疾患で長く入院をしている彼女は、自分が死んだ後の財産の行き場を連絡が取れない一人息子ではなく国への寄付とすると話していた。
そこに目を付けた幹部が、彼女の息子になりきって財産を息子に渡すという遺言状を書かせたのち彼女と本物の息子を始末して、彼女の財産をパッショーネの資金にしようと企んだのだった。
幸か不幸か彼女は生まれつき目が見えず、初めてリゾットが病室に訪れた時も自分の息子だと信じて疑わなかった。それどころか長年音信不通だった一人息子との再会を喜び、生まれ故郷であるシチリアの方言で何時間も思い出話を聞かせてきたのだった。
「嫌な予感は、していたんだ…」
リゾットはソファに座ったまま天井を見上げ、ひとり呟いた。
息子と偽り、毎日朝晩見舞いに行く。病室を訪ね、食事の世話をし、軽口と雑談に付き合う。天気が良ければ彼女の乗った車いすを押して病院内を散歩し、季節の花や肌触りのよい部屋着を選んで彼女とその周りを飾る。その日々の中で、目の見えない彼女が発する懐かしいシチリアの方言。人を愛し、人から愛され、穏やかで鮮やかな時間を紡いでいく。
置いてきた過去と、捨ててきた未来が、そこにはあった。
+++
夜。やはり雪のせいでバスは止まっており、リゾットは最大限の防寒をして病院まで歩いた。途中で寄った花屋は閉店間際で、こんな日はどうせ赤字だからと花束を注文のものより一回り大きく作ってくれた。毎回香りの強いものを、とだけ注文するので何度買っても花の名前を覚えられそうにない。
病室の扉を開けると身体を包む温かい空気に強張っていた筋肉がほぐれていく。彼女はベッドに腰かけて、ちいさな声で歌を歌っていた。聴いたことがあるような気がしたが、どこで聴いたのかは思い出せない。
「何の歌だ? 」
いつものように荷物を置き、尋ねる。
「シチリアの民謡さね。覚えていないかい? 」
彼女は光を捉えない両目をリゾットに向けて答えた。水分を失った瞼が垂れさがっているが、それでも十分に大きな瞳と間にスッと伸びた鼻筋には、若いころは美しかったのだろうという面影が十分に残っている。
シチリアの民謡と聞いてリゾットは思い出した。まだ故郷にいた頃に何度か聴いたことがある。人が集まる場所で、いつも誰かが歌っていた。
「お前がまだ小さいころに“しゃれこうべ”って何って聞いてきてね。意味を教えたらえらく怖がっていたねぇ」
くすくすと笑う彼女を見ていると、子供時代の自分が本当にこの歌を怖がっていたかのような錯覚に陥る。そうして次にこの歌を聴いた時に、母親である彼女の後ろに回って両脚に抱き付きながらスカートに顔をうずめて音楽から隠れようとするのだ。まだ若い彼女が今と同じようにくすくす笑いながら、大丈夫よと言ってリゾットの頭をなでる。
「あぁ、怖かったな。この歌を聞くたびに怯えながら母さんにしがみついていた気がする」
「あの頃のお前は本当に可愛かったのにねぇ。今ではこんな大男になってしまって」
感慨深そうにリゾットを見つめる彼女の視線がむず痒くて、リゾットはやはり残してあった夕食に手を伸ばす。
「照れなくてもいいんだよ。私はね、お前が息子で本当に良かったと思っているんだ。あぁ、そんな顔をしないでおくれ。お前もシチリアーノならこんな時は、俺も貴女の息子で良かったよ、くらいの事は言って欲しいもんだね」
柔らかい眼差しのまま意地悪く微笑まれ、いよいよリゾットは戸惑ってしまう。
時々彼女はこんな風に何もかもが見えているような振る舞いをする。いや、見えて欲しいのかもしれない。息子ではない、本当の自分の姿を見て欲しい。そうした上で、自分という一人の男の手から食事を摂り、軽口を言い合い、庭を回り、お前が息子で良かったと言って欲しい。彼女に認められたい。彼女に選ばれたい。彼女を癒したい。
「あの歌はさ、生前になにも良い事が起こらなかったしゃれこうべがさ、自分の不幸を嘆いている歌なんだ」
リゾットが帰り支度をしていると、ベッドに横たわっていた彼女がぽつりと言った。
「私もさ、同じなんだと思っていたんだよ。この目のせいで長い事独り身で、ようやく巡り会えたお前の父親は子供の顔も見ずに逝っちまうし」
まるで独り言のように零れてくるその言葉を、しかしリゾットは動きを止め、一言も聞き逃すまいとした。
「お前だけは幸せにしたいと張り切ったけど、愛情だけが空回りして結局上手くいかなかった」
本当の息子は十代でパッショーネに入団している。その時から今まで、彼女はどのような気持ちで過ごしてきたのだろうか。リゾットも十八の時以降自分の母親とは会っていない。頭の隅に追いやっていた記憶を少しだけ引っ張り出し、目の前にいる老女に重ねてみる。
「でも、最後にこうして会えたから、きっと私は幸せ者なんだろうねぇ」
疲れてしまったのか、彼女はゆっくりと目を閉じた。リゾットは布団の上に置かれた彼女の手に自身の手を重ねた。俺も貴女に会えて幸せだったよ、と掛けた声は、彼女には届いただろうか。
その晩、彼女の容態は急変した。
+++
二日間の昏睡状態ののち、彼女は旅立った。
結局財産の話は出来なかった。どうしたものかと考えながらリゾットが病室を片付けていると、普段使っていなかった引き出しの中から一通の封筒が出てきた。差出人には彼女の名前。宛先には“愛する息子へ”と書いてある。中には手紙が入っていた。
“愛する息子へ”
驚いているかい? 目の見えない人間がどうして手紙が書けるのかって。お前は時々そんな風に私を見ていることがあったね。でも見くびってもらっちゃあいけないよ。こんな目でも、いや、こんな目だからこそ、私には結構いろんなものが見えているんだ。
お前に会えて幸せだった。これはきっと、直接私の口からも聞かされているだろうね。生きている限り何度でも言いたいよ。この数か月間、お前に会えて幸せだった。
ひとつ心残りなのは、お前の本当の名前を知らないまま死んでしまう事だ。何があって息子のふりをしているのかはわからないが、お前がそう振る舞うのなら私はそれに付き合うよ。ごっこあそびだ。子供の頃もよく遊んだねぇ。お前は警察官に憧れて、いつも泥棒役の私を逮捕してはおもちゃの手錠をかけたもんだ。どうせならお姫様と王子様になって遊んでみたかったよ。僕と結婚してください、なんてプロポーズをお前から受けてみたかったねぇ。
また驚いたかい? だから、私にはいろんなものが見えているのさ。
あぁ、まだまだ書きたいことがうんとあるよ。でもちょっとばかし疲れてきたから、続きはまた今度にしよう。
そういえば、ついぞ使い切ることが出来なかった蓄えが少しだけ残っているんだ。邪魔だっていうなら別だが、そうでなければ使っておくれ。
もう数時間したらお前が会いにきてくれると思うと気持ちが明るくなるよ。覚えておいてくれ。私はお前に会えて幸せだ。
ありがとう。
母
手紙を読み終わったリゾットは、暫くの間何も考えられずに立ち尽くしていた。喉がひどく乾いている。封筒の中を確認すると、息子に全財産を相続させるという遺言状が入っていた。
メローネにシチリア行きの準備をさせなくては。プロシュートの予定も調整しよう。この病室を片付けたあとは役所に行って、幹部へ報告書を書くのだ。
彼女には自分が息子ではないと気づかれていた。信じられない現実を前にして、思考が任務へと逃げていく。ホルマジオとイルーゾォは無事に任務を遂行できただろうか。ギアッチョには次の任務を与えよう。ペッシには雑務を手伝ってもらいたい。
任務の事だけを必死に考える。そろそろこの病室も出なくては。そう思って扉に手を掛けて振り返った瞬間、彼女の歌が聞こえてきた。思考の合間を縫って頭に流れてくる。恐怖で彼女にしがみつく幼い自分。優しく抱きしめる温かい腕。くすくすと笑う優しい声。
彼女は息子ではない自分を、愛してくれた。
リゾットはその場に崩れ落ち、声を殺して泣いた。
大砲の上に しゃれこうべが
うつろな目を ひらいていた
しゃれこうべが ラララいうことにゃ
鐘の音も 聞かずに死んだ
雨にうたれ 風にさらされて
空のはてを にらんでいた
しゃれこうべが ラララいうことにゃ
おふくろにも 会わずに死んだ
春が来ても 夏が過ぎても
誰も花を たむけてくれぬ
しゃれこうべが ラララいうことにゃ
人の愛も 知らずに死んだ
(しゃれこうべと大砲/シシリー民謡)
完