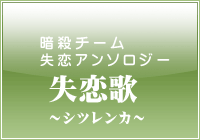どうして、オレじゃダメだった? どうして、どうして。
Sempre libera by ジュリエッタ・S・リュンヌ
華やかで楽しい事が好きだった。
気持ち良く酔える酒が好きだった。
綺麗で遊び上手な女が好きだった。
甘くて刺激的な恋が好きだった。
要は浮ついた馬鹿だったって事だ。
他人よりも恵まれた容姿のせいで、ドブの中で生まれたのと変わらない出自のくせに、女と寝る事が出来るようになった頃にはパーティーを渡り歩く一端のセレブ気取りだった。
親子以上に年の離れた金も心も余裕たっぷりの女から貰った“お小遣い”でハイブランドを装備しては、とびきりの女とショートストーリーのような駆け引きと結果をゲームのように楽しんだり、パパのブラックカードで精一杯背伸びした悪い娘気取りのお嬢様に大人の世界を見せてやったり、どんな時も一人でベッドに入る事はない。子供がぬいぐるみを抱いて寝るように、夜毎女を抱いて寝た。
その中で特に気の合う(体が合う)相手というのは出てくるもので、なんとなくゲームが億劫だったりする時に連絡出来る、彼女はそういう仲間の内の一人だった。自由という名の無責任さを共有できる享楽を趣味とする仲間。
「いい女だな。」
「貴方も素敵よ。」
キスとともに交わされるこんな台詞はパーティーフリークの挨拶みたいなものだが、有名人からそれを受け取る資格があるという事は十分に優越感を満たしてくれる。
今、ダイヤのピアスだけを身につけて腕の中にいる彼女はモデルだ。名前を聞けばファッションに疎い奴でも知ってるだろうから伏せておく。
10代の頃からミラノコレクションにも出ていたトップモデルだったのに、20歳になったばかりで実業家と結婚するも数年で結婚生活は破綻し離婚。今に至る。
「まだ離婚はしてないわよ。別居中」
「もう離婚してるも同然だろ。」
「全然違うわよ。」
天性の美貌にプロポーション。シルクのシーツに覆われて尚隠しきれないその滑らかな曲線ごと、抱きしめて口付ければ極上の味がする。
「ふふっ、くすぐったい。」
少しばかり年上のはずだが、金に糸目を付けず磨き上げた肌の質感と舌足らずな上に幼い話し方で年下のように感じる事が多く庇護欲を掻き立てられる。それでいて気が強くタフな性格でバーやクラブで生意気な小娘とやりあった事も一度や二度ではない。しかもベッドでは大胆で感度は抜群。恋という名の贅沢な遊びを満喫するために生まれて来たような女だった。
反対に夫という男はパーティーで見かけた事があるが冴えなかった。この女を独り占めできるような男じゃない、浮気をされても無理はないとその時はタカを括っていた。
「浮気されたの。あいつがやって良くて私がやっちゃいけないって事はないでしょ?」
散々楽しんだ後の気怠さの中で彼女は吐き捨てるように言った。まだ人妻であった事がわかって「いいのかよ」と聞いた事に対する答えだ。
実業家の夫はグイグイ引っ張っていくタイプの男で、それを男らしさと勘違いしたのだと彼女は結婚の言い訳をした。そしてそれからたいして経っていないにも関わらず彼はよりによって彼女の後輩をベッドルームに引きずり込んだのだ。
正直、驚いた。夫の方が彼女に夢中で結婚したのだと思いこんでいたから。
「やるもんだな。そんなモテる男には見えねぇけど。」
「でしょう?人は見かけによらないのよ。」
「そうだな。」
手を伸ばして彼女の髪に口付ける。
「こんないい女がいるのに。馬鹿な男だ。」
「……。」
その後輩のモデルは寝た事がある。彼女とは比較にならないつまらない女だった。浮気現場を見つかるなんてヘマもそうだが、あんな女のためにこの女を手放すなんてどうかしてるとしか思えない。
「でも俺達だって今見つかれば同じだぜ。」
「平気よ。」
指を絡めて手を押されつけられ、組み敷かれた姿勢で彼女は平然と言ってのける。
「私達に見られて困る事なんてある?」
「ねぇな。」
「あなたみたいな綺麗な男は他にいないわ。プロシュート。」
「光栄だね。美男美女で俺達ならお似合い。」
「冗談でしょ。」
コロコロと笑いながら彼女が首に腕を回すと、二人薔薇の香りのシルクの波間に沈んでいく。
「…あなたが一番いい…」
自分が美しいという過信。賞賛と羨望と憧憬の視線をフラッシュのように浴びては大切なものが見えなくなっていた。
夫には本当は好きな人がいたのよ、と彼女はプロシュートの口から煙草を奪って吸いながら言った。
少なくともモデルという仕事には真摯な彼女は、普段なら肌に悪い煙草は決して口にしない。
繰り返された口付けでルージュが剥げた形良い唇から煙が吐き出される。
「大学の同級生ですって。お互いタイミングを逃して良い友人のままだって夫は言ってたけどどうかしら。未練たらたらって感じだったわ。だったらなんで結婚なんかしたのかしら。」
「そりゃあ男は一人じゃ生きられねぇからな。」
彼女から奪い返した煙草はほんのりと薔薇の移り香がした。
「それは女だってそうよ。」
だからこうして一緒にベッドの中にいる。一人では居たくない、居られないから自由な振りをしては誰かを誘う。
不意に薔薇の香りが強くなる。舌に絡みつくヴェルヴェットの手触り。砂糖菓子のように崩れやすい足元を忘れてハイになるためのフォアプレイ。
「なあ……」
「なあに?」
もし寂しいなら俺が側にいてやると言いかけたが、柄でもないのでやめた。
気が付けば最近は彼女と会ってばかりいる。だからと言って相変わらず恋人なんて関係ではないが、行きずりの関係はなりを潜め、他の女と会うのも久しぶりになっていた。
「素敵よ、プロシュート。駆け出しの下っ端ギャングには見えないわ。」
駆け出しと下っ端という言葉が癪に障って、金だけでは入れない高級なリストランテの食器とシルバーのフォークが乱暴な音を立てる。向かいに座る女は、ムキなるところが可愛いとばかりに微笑んでいる。
さすがに小遣いが底を尽きそうで、久しぶりに声を掛けたスポンサーと買物をし、男女の遊びをしてから食事に来ている。
「褒めているのよ?」
女は自分の買い与えた物が美しい男を更に美しく引き立てている事に満足気に笑った。こういうのは未だに少し照れる。
「…そりゃGrazie。」
「どういたしまして。」
豪華なcenaも終盤に差し掛かり、運ばれて来たdolceに女は少女のような歓声を上げる。女という生き物は幾つになってもどこか女の子のままなのだ。
「そういえば彼女…あのモデルの。」
スプーンを持つ手がピクリと止まったのを見て、女は微かに目を細めた。
「離婚が成立したらしいわ。」
「へぇ。ようやくあの旦那から解放されて完全に自由の身になったわけだ。めでてぇ話じゃねぇか。」
「別れたくないってごねてたのは彼女の方よ。」
迂闊にも驚きがそのまま顔に出てしまった。人生経験豊富な女はやっぱりね、と溜息をつく。
「まさか…」
「最初から夢中なのは彼女の方だけだったの。ゴリ押しで結婚したのはいいけど、やっぱり無理があったのね。」
一人の男に執着する彼女なんて想像も出来なかった。誰よりも美しく華やかで男を振り回しては飛び回る。それが彼女じゃなかったのか?
どれだけの時間、呆然としていたのだろう。気が付けば女は食べ終わってナプキンで口を拭い、自分の皿の上では溶け切ったジェラートとソルベがマーブル模様を描いていた。
「一度くらい素直になってみれば?」
「は?俺はいつだって好きなようにやってるさ。」
「私達と違って彼女はまだ本当の恋が出来るのよ。」
子供のように顔が赤くなるのを感じた。これだから大人の女は苦手だ。こっちがいいように使っているつもりが結局は手のひらの上で転がされている。
「週末のパーティーには来てね。お友達も会えるのを楽しみにしてるし、あなたが居ると華やかでいいわ。じゃあね、プロシュート。」
本当の恋からは引退した女は席を立って頬に軽いキスをすると、悪戯が成功した後のような笑顔で手を振って出て行った。
店を出て時計を見ると、まだ時間は早い。
「プロシュート。これで心置きなく遊べるわ。パーッといかない?」
いつもの彼女ならそう言って来そうなのに、連絡は無い。もしかすると俺が他の女と予定を入れていたから、別の相手と楽しむ事にしたのだろうか?
別に不思議な事じゃない。
今までずっとそうやってお互い自由に相手を変えて楽しんで来た。だが遊び相手の中では一番相性が良くて一番彼女に気に入られているのは自分のはずだった。例えそこに感情などなかったとしても何かあった時の夜は自分を選んでくれるはずだと思っていた。
細く小さな棘が刺さったような痛みを胸の奥に感じる。何故だろう、こんな事は始めてだった。
行きつけのクラブやバーに寄ってみても彼女の姿は無い。
「はい。プロシュート。
彼女と同じような付き合い方をしている別の女が声をかけてきた。さっぱりとして気風のいい女だ。
「久しぶりね。」
本当は彼女を探しに行きたかった。この女に聞けば行き先がわかったかも知れない。何故か側に居たかった。けれどそんなのは自分達には余りにも不似合いな気がして、目の前の女の腰を抱いた。
「よぉ。お前今夜暇?」
「暇よ。」
女は艶っぽい笑顔で瞳を覗き込む。
「あなたの目って相変わらず綺麗ね。サフィールみたいで好きよ。」
柔く甘い温室の花とは違う颯爽としたグリーンとシトラスの香りが鼻腔を満たすがそれはすぐに遠ざかった。
「でも今日はやめておくわ。気分じゃないの。」
女は男よりも嗅覚が働く。その言葉が無意識に他の女の事を考えていた事への気遣いだともわかったのは随分経ってからだった。
トップモデルの自殺未遂というニュースを見たのは翌朝のベッドの中だ。
一晩中連絡を待っての一人寝で、寝不足の不貞腐れた気分まま寝ぼけ眼でテレビをつけたら彼女の写真が映っていた。つい最近まで化粧品のポスターに使われていたやつだ。
「な…んで。」
自殺未遂とはっきり言っていたわけではない。彼女は酒を飲んだ後、酔っていたのかいつも飲んでいる睡眠薬を多量に摂取してしまい病院に運ばれた。
運良く、意識を失って倒れているところを家政婦に見つかったらしい。ニュースでは彼女の夫が、学生時代からの友人と既に同居している事も伝えていた。
自分の知っている彼女の話だとは思えなかった。
彼女はどんな時でも誰よりも美しく人の輪の中心にいた。傲慢と我儘がよく似合ってダイヤモンドのように傷つかない、そういう女だったはずだ。
例え落ち込むような事があったとしても、慰めてくれる人は数え切れないくらいにいるはずなのに、何故だ。
それらの全てよりもたった一人の男が、あの冴えない男が良かったのか?
あの男じゃなきゃダメなのか?
なんでー
俺じゃダメなのか?
行ってみた病院はマスコミと関係者でごった返していた。
人混みをすり抜けて受付までなんとか辿り着き、彼女に面会したい旨を告げた。
「どういったご関係の方ですか?」
「ご関係…」
家族でも恋人でも、仕事仲間でも無い。
「友人だ。」
本当は抱き合ってばかりで友人と呼べるほどには話をした事なんてないが苦肉の策だった。
「お名前は?」
名を告げると受付嬢はパラパラとバインダーに挟んだリストをめくった。
「聞いていませんね。申し訳ありませんがお引き取り願えますか?」
横をパーティーで何度か見た顔が名前を告げてはすんなり通り過ぎて行く。確かファッション業界のやつだった。
受付嬢は次から次へとやって来る来客に、もうこちらを見る事は無かった。
彼女にとって俺は飲んだシャンパンと変わらない程度の存在で、どうせ飲むなら美味くて洒落た物が良かったというだけの事だ。
無理もない。
どんなに肌を重ねても彼女の孤独は埋められなかった。それを見抜けずただはしゃいでいるような男に、本気で恋する女などいない。
それからは自然とパーティーから足が遠のき、“駆け出しの下っ端ギャング”としての仕事に精進するようになった。
・
・
・
・
・
「どうしたんですかい?兄貴。」
急に口数の少なくなったプロシュートを心配してペッシが声を掛ける。
「なんでもねぇよ。」
プロシュートは読んでいたタブロイド紙を無造作にカフェのテーブルに置いた。
「行くぞ、ペッシ!」
捨てられたタブロイド紙の片隅には、小さく元人気モデルの再婚の記事が載っていて、悪意のこもった文章の隣で、写真の花嫁は穏やかに幸せそうな笑顔を見せていた。
完