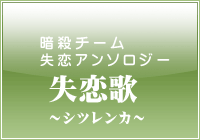アンタがいたから、オレは元気になれたんだ。
憧れの花嫁 by明日狩り
オレが物心ついた頃には、祖国はもう戦争の気配が濃厚で引き返せないところまで来ていた。貴族の末裔の生まれなんでそれなりに豊かな幼少時代を送ったが、なんだかんだで結局戦争に巻き込まれて、家にも戻れなくなり、気がつけば独りぼっちになって終戦を迎えていた。誰にも頼らずにあの国のあの時代を生き延びるのは相当大変だったが、まあ生きるためなら何でもできた頃だ。オレみたいな人間には逆に合っていたのかもしれない。それともあんな時代をガツガツと生き延びてきたからこそ、こんなになっちまったのか? どっちとも言えねぇな。
ともあれ、滅茶苦茶な戦争がようやく終わったばかりだった。祖国は疲弊し、人々も荒んでボロボロだった。全てのベクトルが「食う」の一点に集約されて、とにかく腹がふくれるってことが第一、それ以外のことは「食えない」という意味では何もかもが二の次だった。特にオレみたいな天涯孤独の奴は食うだけでも精いっぱいで、飢え死にしないために生きてるような、そんな日々が続いていた。
だから、その店のショーウィンドウが目に入ったことそれ自体が、オレにとっては奇妙なことだったんだ。
「…………………………へぇ」
あちこちに戦火の爪痕が生々しく残る街角で、崩れかけた服屋のひび割れたショーウィンドウに立っていたのが『彼女』だった。焼け跡から拾ってきたとおぼしき薄汚れたマネキンが、やけに真っ白で綺麗なウェディングドレスを着ている。そのちぐはぐな感じが奇妙で思わず足を止めた。
その日はクソみたいな傷痍軍人の言いなりになって家財道具を運ぶ手伝いをした後で、ようやく手に入れた金で飯を食いに行く途中だった。朝から丸一日食べていない腹がぐぅ……と鳴って、飯を催促する。だけどオレは一瞬で何もかもを忘れちまった阿呆みたいに、じっと『彼女』に見入っていた。
(…………………………)
レースで覆われたその純白のドレスは、首から腕から肌をすっかりと覆う長袖のデザインだった。体にピッタリと沿い、膝の辺りから下がふわりとマーメイドの尻尾のように広がっている。清純なようでいて艶麗、肌は見せないけれどボディラインはくっきりと見せるその矛盾。片手にはブーケに見立てたフリルの丸い飾りを携えている。どこを見ているかも分からない、無表情な顔。少し上を見上げているその視線の先に、花婿でも見えているんだろうか。
「……………………いいじゃん」
オレはにっこり笑って、『彼女』を見上げた。少し高いショーウィンドウに立っている『彼女』は、まだ今ほど背が伸びていなかったオレよりずっと上の方にいて、足下で見上げているオレのことなんか眼中にないようだった。だけどオレは一目で『彼女』のことが気に入った。
頬は煤けて汚れていても、凛として誇りを失わない女の顔をしている。『彼女』が身にまとっているドレスは謎めいていて、男を誘っているのか拒絶しているのか判然としない。その視線の先には本当に決まった旦那がいるのかどうか、ひょっとしたらソイツから逃げ出して来たところなんじゃないだろうか。もしこの『彼女』が無理やりどこかの男とつがわされそうになり、逃げ出して来たっていうんだったら、オレは絶対に『彼女』の手を取って引き寄せるだろうな、なんてことすら考えた。
「いい女だな、アンタ」
人間がただの動物のようになり果てて餌を探し回る街の片隅で、食うことなんかには目もくれずに幸せを追いかけている『彼女』は、美しかった。ただの薄汚れたマネキンがウェディングドレスを着ているだけなのに、オレにはまるで女神かなにかのように思えたんだ。
おそらく、自分では気付いていなかったが、あの頃のオレも人並みに疲弊していたんだと思う。自分ではすっかり一人前で独り立ちしているつもりだったが、まだまだ心は疲れ、悲しみ、どこかで折れかけていたんだろう。そんな壊れかけたオレの心に舞い降りた女神が『彼女』だった。
オレは『彼女』に投げキッスを贈り、ウィンドウを離れた。いつもの店で安い飯を食い、ケンカを売ってきた奴とひとしきり揉めて、殴り合いになる前にうまいことかわして店を出て来たその帰り道、ねぐらへ戻るのに少しだけ寄り道をして、もう一度『彼女』の顔を見に行ったりした。
* * * * * * * * * *
それ以来、その店のショーウィンドウにいる『彼女』に会うのがオレの日課になった。朝、その日の小銭を稼ぎに行く時。昼、何かの用事で通りがかった時。夜、飯を食ってねぐらへ帰る時。
「おはよう、お嬢さん」
「こんにちは、お嬢さん」
「こんばんは、お嬢さん」
通りすがりにあいさつをするだけだったが、それがオレにとっての人間らしい生活の象徴みたいになっていた。ウェディングドレスを着ている奥さんに「お嬢さん」はおかしいかもしれないが、いつまでも若く美しい『彼女』はまだまだ奥さんというふうではなかったし、それに『彼女』の旦那だって見たことがない。だからオレとしては『彼女』はまだ未婚の女性で、ひょっとしたらその隣に立つのは自分なんじゃないかという希望を胸に秘めていた。
勘違いしないでもらいたいんだが、当然、マネキンの『彼女』と本気で結婚しようなんて思っちゃいないぜ? 女は触れば温かくて柔らかいのが取り柄だし、そういうものと触れ合うことだってもう知っていた。ただ、憧れの存在が独身か人妻かっていうのは大きな問題で、男ってのは「独身女性は皆、自分の恋人候補」みたいに思いたいもんなんだ。イエスの母親が処女懐胎して教会に飾られてるのだって、どうせ見る男どもが気持ちよく憧れを持つために決まってる。
そう、教会のマリア様を見るのが励みになる奴だっているだろう。オレにとってはその街角のショーウィンドウに立つ『彼女』が励みであり、憧れであり、何と言うか生活の「張り」みたいなもんだった。だから別にどうこうしようなんて気はなくて、ただ「花婿の席が空いているであろう『彼女』」という存在に心がときめく。孤独なオレにも、毎日あいさつに行ける相手がいる。それが嬉しかったんだ。
けれど、そんな生活も長くは続かなかった。オレはいろんな悪事やらややこしい問題やらを抱えていて、その街を捨てて別の場所へ行かなくちゃならなくなった。もっとも、その街へ来るまでもそんな生活が続いていたし、各地を転々とする生き方しかできなかった。だから街を出る時、ほんのわずかな全財産を鞄ひとつに詰め込んで、オレはやっぱり最後に『彼女』にあいさつに行った。
「よう、お嬢さん。ご機嫌麗しゅう」
夕日を浴びて赤くきらめく『彼女』は、やっぱりいつものようにすこし上を見つめて、足下のオレには目もくれなかった。今日くらいはオレの方を見てくれないかな、なんてちょっぴりセンチメンタルなことも思ってみたが、相手はただの人形だ。そんなわけがない。
「たぶん、これでお別れだ。残念だけど、あんたの花婿にゃあなれなかったな」
もちろん『彼女』は何も言わない。何も答えない。物言わぬ人形に話しかけている自分がおかしくて、オレはクックッと自嘲した。
「さよなら、お嬢さん。あんたはいつまでも美しいままでいてくれよ」
そう言って、オレはその街を後にした。
* * * * * * * * * *
あれからずいぶんといろんな国を回った。一つの場所へ留まることができないオレは、ヨーロッパ中の国々を点々としながら悪いことばかりをやらかして生き延びていた。そうして巡り巡って最後にイタリアに落ち着き、パッショーネというギャング組織の暗殺チームに収まって、決まった家に住みながら相変わらず悪事で飯を食っていた。
あるとき、その暗殺チームのシゴトで祖国に行くことになった。懐かしい国だ。あの街を出てから二度と戻ることはなかったから、何年ぶりになるだろうか。久し振りの祖国へ戻り、あの頃とは比べものにならないほど復興した街並みを見て、さすがに感傷的になった。
「ま、これだけ長いこと離れてりゃ、当然か。……しかし国民性は変わらねえなぁ。クソ真面目な仏頂面した奴らばっかりだぜ」
この国の純血種であるはずのオレだが、イタリアの居心地の良さにすっかりハマり込んでいて、自分は身も心もイタリアーノなんだという気がしてくる。祖国のなじめなさにちょっぴり辟易しながら街を歩き、ふと通りすがった街の一角で既視感を覚えた。
「………………? おいおい、こりゃあ……よォ……」
そこを通ったのはたまたまだった。オレが立ち去ったあの街じゃあない、全然別の地方の初めて来る都市だ。それなのに綺麗なショーウィンドウが並ぶ通り沿いのその店には、ひどく見覚えのある懐かしい姿がひっそりと立っていた。
「……お嬢さん、どうしてこんなところにいるんだい?」
正面に立つ美しい二体のマネキンに主役を譲り、まるでカーテンに身を隠すようにして『彼女』はいた。よくよく注意して見なければ分からないほどひっそりと奥に佇み、ウィンドウの中に掛けられたカーテンの隙間から表通りを窺うように立っている。
どうして『彼女』がここにいるのか。そんな疑問よりも先に、オレは「誰が彼女をこんな目に遭わせたのか」ということに腹を立てていた。これじゃあ『彼女』があんまり可哀想じゃねえか。日陰者のように奥に追いやるくらいなら、いっそ倉庫にでも引っ込めちまえばいいものを、まるで人気者を引き立てるために無理やり立たされているように見える。オレは思わず店に飛び込んだ。
「いらっしゃいませ」
店にいたのは初老の男だった。他に従業員がいる様子もなく、おそらくこの男が一人でやっているのだろう。狭い店内はドレスや装飾品であふれ、誰かが幸せになるための特別な日の道具ばかりが並べられていた。
「表のお嬢さんのことなんだが」
カッとなっていたオレはついうっかり「お嬢さん」と口走ったが、男は別におかしいとも思わなかったらしく、愛想笑いもせずに真面目にうなずいた。
「ええ、どちらのドレスの娘でしょう?」
「違う、どっちでもねぇ。奥に引っ込んでるあの『お嬢さん』だ」
「……………………」
そう言うと、男はハッと息を呑んでオレを見た。不思議そうに、ほんのわずかばかり小首をかしげて、やはり生真面目そうな顔でこう言う。
「……彼女が、どうかしましたか?」
「どういうわけで、あんな場所に立たせてるんだ?」
「……お見苦しかったでしょうか? あまり目立たぬようにしているつもりですが、不快でしたらお詫び申し上げます。確かに少し古いドレスではありますが、あれは……」
「誰も見苦しいだなんて言ってねえ。オレが不快なのは、なんで彼女をあんな日陰に押し込んで見せ物にしておくのか、ってことだ」
「……………………」
オレがそう言うと、店主は驚きで目を丸くして押し黙った。そりゃあそうだろう。こんな訳のわからねぇイチャモンを、見るからにカタギじゃあねえオレみたいな奴に言われたら、誰だってそうなる。店主の表情を見て少し冷静さを取り戻したオレは、視線を逸らして言い訳がましくこう言った。
「いや、別に何をどうしたいって訳じゃあねえんだ。ただ、あんな今風の花嫁二人の後ろでよォ、日陰者みてーに華やかな表舞台を眺めてる、ってのはちょっと可哀想なんじゃねえかな、と思ってよ」
「…………そんな風に見えましたか。それは申し訳ございません」
「いや、だからどうだって訳じゃねえんだが……」
「こちらへお越し下さい」
店主はうやうやしく店の奥へ進み、大きな棚の後ろへオレを案内した。
「…………これは?」
「これが、表のショーウィンドウから見えてしまっているのですね」
そこは古めかしい衣装や道具がいくつか並べられ、【当店のあゆみ】という小さな展示コーナーになっていた。先代が興した店を守り抜き、戦中戦後も何とか生き延びて、今の店になったという。その展示の中央に、まるでマリア像でも奉るかのように立っていたのが、『彼女』だった。
店主が接客する店員からただの男の口調になり、しんみりと語る。
「もう表に飾るには古びてしまいましたが、私にとって大切なウェディングドレスなのです。ここへこうして飾っておりますが、少しでも表の様子を彼女に見せてやりたくて、こっそりとカーテンを開けています。今まで誰にも指摘されたことはありませんでしたが……見る人が見れば、汚いマネキンが視界に入ることもあるのですね。大変失礼致しました」
「いや、ほとんど目立たねぇ。多分誰も気付かねえよ…………オレ以外はな」
「そうですか。ですがお見苦しいところを」
「いいんだ。あんまり『彼女』を卑下してやるなよ。……綺麗なお嬢さんじゃねえか」
オレは肩の力を抜いてそう言った。すると男はフッと表情を和らげ、初めて笑顔になった。
「お嬢さん、ですか。……もうすっかりいい年ですよ」
「ああ、そうかもな。だってオレがあの街で初めて『彼女』に出会ったのは、もう遙か昔のことだ」
「まさか! ……あの頃をご存知なのですか?」
男は不思議そうにオレを見た。ああ、そうなんだ。オレはあの頃から『彼女』を知ってるんだよ。
「まあな」
「……そうですか。それはそれは。彼女にそんな古い知人がいたとは、私も知りませんでした。フフ……嬉しいこともあるものです」
そう言って男はじっと『彼女』を見た。煤けた頬、黄ばんだドレス、けれど少し上を見上げる『彼女』のまなざしは何も変わっていない。二人で静かに『彼女』を眺めていると、やがて男の目に涙が浮かんできた。
「ありがたいことです。彼女を昔から知る『友人』が訪ねてきてくれるなんて……」
「変な客ですまねぇな」
「いいえ、本当に嬉しいのです。まるで彼女が生きていて、私の知らない友達を連れてきてくれたかのような気がします」
そう言って男は零れた涙をハンカチで拭った。
オレはふと、ひとつの予感に囚われた。
「なあ」
「…………はい」
「『彼女』が着ているのは、誰のウェディングドレスなんだ?」
黄ばんだドレスを誇り高く着こなす『彼女』を見つめながら尋ねると、男は涙混じりの震える声でこう答えた。
「………………私の、妻になるはずの女性でした」
「……戦争か?」
「ええ、あんな時代でしたから。結婚の約束をして、ウェディングドレスまで用意したのに、私は兵役に取られた。そうして戦争が終わって命からがら戻ってきたら、彼女はもう……」
「そんな時代だったもんな」
「そうですね。戦場に行った私は生き延びて帰り、街で待っていた彼女はウェディングドレスを着ないままこの世を去った。それがあんまり理不尽で、悔しくて…………ッ」
絞り出すような男泣きの声を聞きながら、オレはただじっと『彼女』を見つめていた。
(ああ、アンタはあの頃からもう人妻だったんだなァ……。いい女だもんな。そうか。そりゃあそうだ)
「なあ、アンタの嫁さんは本当にいい女だな。オレは『彼女』がいたから、あの戦後の荒んだ時代に少しでも心を慰められたんだ。まだガキだったからな。街角のショーウィンドウに立つ綺麗なお嬢さんを見るだけで嬉しかった……」
そう言うと、男は声を殺しながら泣いた。
「アンタ、男泣かせのいい女だなァ……」
男二人を心底惚れさせて、『彼女』は凛と立っている。やっぱりオレが見込んだ女に間違いはなかったな、と、オレは泣きたいような笑いたいような妙な気分で、ただじっと『彼女』が見つめる視線の先を眺めていた。
完