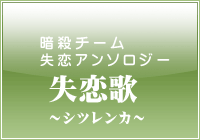無理やり付き合わされているつもりだったけど、案外楽しかったのかもしれない。
おれの王女さま by明日狩り
小さな頃から図体だけはでっかく、そのくせ気が小さくてオドオドした子供だった。年上からは目を付けられ、年下からは怖がられて、だからペッシには気の許せる友達というものが一人もいない。いつも年上の不良たちに連れ回されて一緒に悪さをするか、さもなければ一人で釣りをしていることも多かった。身体が大きいせいで悪目立ちしているが、ペッシは本当は静かに釣りをするのが好きなおとなしい少年だった。
そんなペッシの日々が突然変わったのは、彼女が来てからだ。
ペッシが母親と住んでいる家の隣には、元社長の別宅だった大きなお屋敷があるのだが、長らく空き家になっていた。ここらはそれほど治安が良いわけでもなく、こんな場所に大きな屋敷を買いたいという物好きな人間は少なかったのだろう。それでも供給があれば需要はあるもので、とうとうある日このお屋敷に新しい住人が引っ越してきた。
「あたし、王女さまなの」
車から降りてきた少女は、ペッシを見るなり小走りに駆け寄ってきて、急にそう言い放った。
「えっ……?」
あまりに唐突だったので、ペッシは呆然としてでくの坊のように突っ立ったまま、自分の背丈の半分ほどにも満たない幼い少女を穴が開くほど眺めた。
ウェーブのかかったブロンドの髪を長く伸ばしている。
白い肌にはそこらの子供のようなそばかすもなくて、お人形のように綺麗だ。
ほんの少しでも身じろぎをしたら何かに引っかけて破れてしまいそうな華奢なレースを使ったドレスを身にまとい、まるで絵本のお姫様のような格好をしていた。
小さな少女は、十二歳になるペッシの半分ほどの年齢だろうか。にもかかわらず、まるで自分が上の立場の人間であるかのように、臆することなくペッシを見上げる。
「あたしの言うことは何でも聞くのよ?」
「えっ?」
「ねえ、王女に名前も名乗らないのは失礼じゃない? 名前、なんて言うのよ」
「え、あ、ぺ、ペッシ……」
とっさにそう答えてから、それが自分のあだ名だったことを思い出す。いつも魚釣りばかりしているから「魚(ペッシ)」と呼ばれているのだが、少女は何の疑問も持たなかったようで「ペッシね」とだけ言った。
「あたしは王女さま」
「それ、名前なのかい?」
「名前よ。そう呼べばいいの」
「そう」
「さあペッシ、案内してちょうだい」
少女はふんぞり返って片手を差し出し、生意気そうに顎をくっと持ち上げてペッシを見た。
「え?」
「案内よ。この街を案内しなさい」
「案内? 案内って、どこへ行きたいんだい?」
「どこでもいいわ。あなたが知ってるところで、私にふさわしいと思う場所へ連れて行きなさい」
いきなりそう命令されて、ペッシは困惑した。辺りを見回すと、引っ越しのあいさつをしている少女の両親と自分の母親が目に入った。母親は「あらあら」と言いながら、
「もう仲良くなったの? 親切にしてあげるのよ」
と呑気なことを言う。少女の両親らしき人は見るからに金持ちそうな紳士淑女で、これまた、
「うちの娘を宜しく頼むよ、ナイト君」
などと言っている。どうやら拒否する権利はペッシにはないようだ。
仕方なく少女の手を取り、その場を離れる。
「どこへ行くの?」
「うーん……おれの知ってる場所なんて、街とか、学校くらいだしなぁ」
「街? 街なんて嫌」
少女は顔をしかめた。こんな少女を連れて街へ出ればいつもの不良仲間に何を言われるか分からないのだから、言われるまでもなくそんな場所へ連れて行くつもりはない。
「けど、街がダメだとなると、あとはもう川とかしかないよ」
釣りをするための秘密の河原があるのだが、そんな場所へ人形のような格好の幼い少女を連れて行くのはそぐわないとさすがのペッシにも分かっている。それに自分だけの秘密の釣り場を誰かに見せるのは嫌だった。
だが、贅沢なレースをふんだんに使ったドレスを着た少女は、目を輝かせて言った。
「川? いいじゃない、そこへ案内してよ」
「えええ? お、面白くなんかないよ? 川だよ、何にもないよ」
「水が流れているのでしょう?」
「そうだけど……ボートとかそういうのもないよ?」
「ボートなんかなくたって良いの。川は好きだわ。さあ、行きましょう」
どういうわけか少女はノリノリだ。ペッシは仕方なく、少女の手を引いていつもの河原を目指して歩いた。
* * * * * * * * * *
ペッシと少女は、それ以来毎日一緒に遊ぶようになった。少女はペッシの遊びに大いに興味を示し、釣りや水遊び、木登り、草で船を作って川で競争すること、石を水面に投げて飛ばすテクニック、食べられる木の実、鳥を捕る罠の仕掛け方、カブトムシが集まる木の場所まで、何でも楽しそうに覚えていった。ドレスが汚れないように、ペッシは自分のお古のシャツとズボンを少女に貸してやり、彼女はいつも草葉の陰でその「衣装」に着替えた。
「これは衣装なの。王女が学習するときに必要な、衣装なのよ」
「そうなのかなぁ。おれのお古だよ?」
「衣装。衣装ったら衣装。わかる?」
「わかったよ……」
ペッシはしぶしぶうなずいた。
王女に逆らうとそれはそれは恐ろしい目に遭うことをペッシは知っている。一度、「今日は遊びに行かない」と言ったことがあるのだが、王女はまるで火山の噴火のように泣き叫び、暴れ出し、こんな小さな身体のどこにそんな力があるのかと驚くほどの勢いでペッシに殴りかかってきた。とにかく気性が激しく、小心者のペッシはそれだけで気圧されてしまい、この小さな王女さまの命令に逆らえなくなっている。
「あたしのパパは、王さまなのよ」
ペッシの母に持たされた弁当のサンドイッチを食べながら、二人は河原で休日を過ごしていた。ペッシの母は彼女の両親から子守を任されているらしく、その任務が丸ごと息子のペッシに下請けに出されている。少女は粗末なサンドイッチを美味しそうに食べながら、自慢げに語った。
「どこの国の王様なの?」
「ユイツムニの王国なの」
「それが国の名前かい?」
「そうよ。パパが言ってるの。パパは『ユイツムニ』の王さまで、あたしは『ユイツムニ』の王女さまなんだって」
実際、彼女には一国の王女のような気品があった。気高さ、というのだろうか。何者にも屈しない強さを芯に秘めていて、弱虫のペッシにはそれが羨ましく感じられた。
(おれ、こんな小さい子にまで顎で使われて……。情けねぇなあ……)
どこまでも負け犬にしかなれないペッシは、しゅんとして肩を落とした。男友達どころか、小さな女の子にさえ逆らえない。
(……でも、この子を力で負かしたって、多分それじゃあ何にも変わらないんだろう…………)
腕力に訴えればきっと勝てるのだろう。だがそれでは本当に「勝った」ことにはならない。ペッシにはなんとなくそのことが分かっていた。
「さ、ご飯を食べたらまた学習よ。王女さまはたくさんたくさん、学習しなくちゃならないの!」
「ま、待ってよ。おれまだ食べ終わってないよ……!」
「ペッシは愚図ねぇ。仕方ないわ。王女さまが食後のお茶を飲み終わるまでに、食べ切っちゃうのよ。そうでなかったらお仕置きするんだから」
王女さまは一度浮かせかけた腰をもう一度石の上へ下ろし、水筒からぬるいお茶を出して飲み始める。あわてて粉っぽいサンドイッチをほおばったが、それを飲み下すためのお茶が王女さまの手にあることに気付いてペッシは目を白黒させた。
「あ、あの……」
「なあに? 食べ終わった?」
「お、お茶……」
「王女さまが飲んでるんだから、ダメよ。当然じゃない。ペッシは待ってて」
そもそもペッシが持ってきたお茶なのに、少女はフンとかわいく唇を尖らせて手を引っ込めた。こんなことをされてもあまり腹が立たない自分が情けなくて、ペッシは口をもぐもぐさせながらなんとかサンドイッチを飲み込んだ。
(あーあー、おれってほんとにダメだなぁ……)
それでも、王女さまを放っておくなんてことは考えられない。そんなことをすれば母が失望するだろうし、何よりこの傲慢で我が侭な王女さまが烈火の如くお怒りになるのは目に見えているからだ。
* * * * * * * * * *
そうして夏が過ぎ、秋も深まったある日のこと。
「あれ……?」
珍しく朝寝坊をして、ペッシはぼんやりと時計を見た。もうすぐ昼になる。
「おかしいな」
いつもならこの時間には起きていて、外へ遊びに行っているはずだ。どうして今日に限って寝過ごしたんだろう……と寝ぼけた頭で考えながら、ようやくその理由に思い至る。
「あの子、来なかったのか」
休みの日には必ず、あの少女が起こしに来ていた。
「何時まで寝てるつもりなの! 王女さまに起こしていただくなんて、光栄だと思いなさいッ!」
そんなことを言いながら布団を引き剥がされ、ベッドから蹴落とされて、しぶしぶ遊びに行く。それが休日の日課になっていて、朝自分で起きるということがすっかりなくなっていた。
「どうしたんだろう?」
おかしいな、と思い、服を着替えて外へ出る。すると、家の前がなんだか騒がしかった。
「あっ、ペッシ!」
母が青ざめた顔で人だかりから離れ、唐突にペッシを抱きしめた。
「え? どうしたの? 何かあった?」
「ううん。家に入ってなさい。ちょっと騒々しいから」
そう言うと母はペッシの頭を抱きしめたまま、まるで視界を塞ぐように身体を引きずって家へ入っていった。
「ねえ、何? 何かあったの? お隣に何かあったんだろう?」
「いいの。大丈夫だから。お引っ越ししたらしいわ」
「嘘だ! ねえ、あの子はどうなったの? あの子は?」
「私にも分からないわ! でも外へ出ない方が良いの」
母は少し震えていた。ただ事ではない、ということが子供にも肌で感じられ、同時にあの子のことが心配でペッシは叫び出したいほどの不安に駆られた。
「ねえ……どうなっちゃったの? あの子は?」
「急にお引っ越しをすることになったんですって」
「あの子は?」
「あの子も一緒よ」
「お別れを言わなきゃ!」
そう言って飛び出そうとするペッシをきつく抱きしめ、母は首を横に振った。
「いいえ、もう行ってしまったの。もうあそこにはいないわ」
「そ……そうなの? 何も言わずに行ってしまったのかい?」
「ええ、急な話だったから。……あんたによろしくって言ってたわ」
母はきつく目を閉じ、震える声でそう言った。
(嘘だ)
いくらペッシが子供だからといって、そのくらいのことはもう分かる年齢だ。そして母の精いっぱいの嘘を振り切って外へ飛び出すほど無分別でもなかった。
(あの子は……)
きっと、とても悲しいことが起きた。そのことがペッシには分かってしまった。
(あの子は、同じくらいの年の友達がいなかった。女の子も、男だって、おれしか友達はいなかったんだ。本当ならお人形で遊んだり、おしゃれをして本を読んだり、そういうことだってしたかったに違いない。それでもおれしか友達はいなかったから、おれの遊びにずっとくっついてきた。男の遊びなのに楽しそうにしてて、嫌なことなんて何にもないみたいだった)
あの子の親がまともな人間でないことは、ペッシにも分かっていた。不良仲間があの家は「ギャングの家」だと言っていたし、学校の子供たちも怖がって近づかなかった。だからあの少女に近づく子供は一人としていなかった。……ペッシ以外は。
グスッ、と鼻をすすって、ペッシは母に尋ねた。
「ねえ、あの子が言っていたんだけど」
「なに?」
「あの子は『ユイツムニ』の王国に住んでるんだって。『ユイツムニ』って何かなぁ?」
「唯一無二のこと? それはね、『かけがえのない、たったひとつのもの』っていう意味よ」
「そう……」
少女は『唯一無二』の王国の王女さまだった。親が危険なギャングで、傲慢な性格に育ったせいか、友達もできない。服は豊かだったけれど、遊び方も、楽しみ方も、何も知らなかった。
(あの子はそれでも楽しそうだった。あの子はちゃんと、自分の国の王女さまだったんだ)
守りたかった。
けれど、守れなかった。
王女を失った騎士は力なくうなだれ、滅びた王国に思いを馳せていた。
【完】