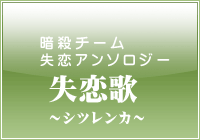なんとなく、なりゆきで、ずるずると。
嵐とキスと、その後で byヤミ
雷が鳴る。横殴りの雨は容赦なく体に打ち付けられる。裸足で走り続けたため、足の裏は切れて血が滲んでいるだろう。が、今はもう感覚が無い。それは裸にバスタオル一枚というこの身体も同じことで、痛みも寒さも冷たさも随分前から何も感じない。ただただ疲労だけが足取りを重くしたが、それでも私は走り続けた。どれだけの時間が経ったのか。そしていよいよ限界というところまで走って動けなくなり、明かりの消えた街のどこか知らない裏道で私は気を失った。
+++
メローネはソファから起き上がると大きく伸びをした。一晩の間に身体はだいぶ凝ってしまっている。そのままシャワーを浴びて身支度をし、新聞を買うために駅の方へ出かける。ついでにメルカートに寄って新鮮な野菜とチーズ、パンを数種類調達した。自宅へ戻ったらパソコンを開いてリゾットへ連絡をする。確か今は任務のはずだから電話よりメールの方が良いだろう。しばらくの間アジトではなく個人で借りているこの部屋で暮らすということと、任務の依頼や報告はメールでやり取りをするということを簡潔に伝える。普段から思い付きで行動をすることの多い自分だから、きっと深く詮索されずに了承してもらえるだろう。
一連の事を手際よくこなし、軽く伸びをしながらベッドを見る。ワンルームのこの部屋はリビングと寝室がパーテーションで仕切られているだけだ。そこに眠る女はまだ起きる気配が無い。昨夜、任務の帰りに見つけた女。人目を避けるために選んだ裏道で蹲るようにして倒れていた。ぐっしょりと濡れたバスタオルを張り付けた体は冷え切っていて、足からは血が流れている。死んでいるのかと思ったが、かすかに体が上下しているのが分かった。しかし、このまま放置していればいずれ死んでしまうだろう。治安の悪い場所だ。死んでしまうより酷いことになるかもしれない。
本来ならこんなものにかかわってはいけない。何らかの事件に巻き込まれている事は確実だし、下手に手出しをして自分の命を落とす可能性だってある。が、気づいた時には女を担ぎ上げ、帰るはずだったアジトではなくメローネ個人のアパートに向かって歩き出していた。
+++
頭が割れるんじゃないかというほどの頭痛とともに、ぼんやりと意識が浮上した。ゆっくりと目を開けると、閉められたままのカーテンが見えた。隙間から光が漏れているところからすると、今はもう昼近い時間だろう。頭痛だけでなく、全身がひどく痛む。どうやら私はベッドに寝かされているようだ。ゆっくりと体の向きを変え、自分が今どんな状況なのかを考える。意識を失う前、私は裸で嵐の中を走り続けた。追いかけてきた男は撒いたのだろうか。裏道で蹲ったところまでは覚えているが、そのあとの記憶がない。誰かに保護されたのだろうか。
「Ciao! 目が覚めた?体の調子は良好かい?」
気が付くと、金髪の男がベッドの横に立っていた。アシンメトリーに切られた髪を揺らしながら私の顔を覗き込んでくる。
「昨日は災難だったね。俺が見つけてあげなきゃアンタあのまま死んでいたよ。アンタが倒れていた場所どこだかわかる?女モンの下着を売っている店とオーダーアクセサリーの店の間の小道さ。そんなところに素っ裸の女の死体って、なんだかねぇ。あぁ、俺は大丈夫。拾っといてなんだけど、アンタにはこれっぽっちも興味ないから。いや、ゲイって意味じゃあないからね?俺も詮索されちゃ困ることがゴロゴロあるからさ、お互い様ってことで」
そこまでを一息で話すと、私の額に手を置いた。大きくて少しだけ冷たい掌が心地よい。
「熱があるみたいだね。身体は蒸しタオルで拭いたけど、髪を洗うことは出来なかったからドライヤーで乾かすだけにしておいたよ。もし動けるならシャワーを浴びるといい。ミネストローネは好き?ブリオッシュとカンパーニュもあるから好きな方を選んで。ヨーグルトはバナナとラズベリーを買ったけど、俺はどっちも好きじゃあないから両方あげる。風邪薬は切らしてるんだ。でも栄養をつければすぐに元気になるよ」
そう言うと男はどこかへ行ってしまった。私は身体の痛みをこらえながらゆっくりと上半身を起こす。部屋は暖房が効いていて温かい。裸だった身体には綿のシャツが着せられていた。あの男のものだろうか。着心地が良く、かすかに洗剤の匂いがする。布団をめくると、包帯が巻かれた脚が見えた。
私が自分の身体を眺めていると、男が水を持って戻ってきた。そういえばひどく喉が渇いている。
飲めそう?そう聞かれて、小さくうなずく。コップを取ろうと伸ばした手を優しく止められ、疑問に思い顔を上げる。男はコップを取って自分の口に水を含むと、そのまま私に口移しで水を飲ませた。トロトロと口内に流れてくる水は冷たくて、でも上手く飲み込むことが出来ずに口の端から垂れていく。唇が離れる瞬間、男がかすかに笑ったのが分かった。
「毒が入っていないっていう証拠にね」
そう言いながら親指で私の口元を拭う。触れる指先はやっぱり少しだけ冷たかった。
+++
彼女との生活が始まった。初日こそほとんど喋ることのなかった彼女だが、何かにつけて話しかけ、一緒に食事をし、足の傷を診てやっているうちにすっかりメローネに心を開き、今では自分からあれこれと接してくるようになった。
「そろそろ起きたらどう?掃除をしたいからソファから降りてほしいの」
「ん〜…。あとちょっとだけ…。知ってるだろ。帰って来たの朝の四時だぜ…?」
「でももう十時よ。六時間も寝れば充分よ」
「なぁ、あと五分…」
「ダメよ、今すぐ」
メローネがどんな仕事をしているのかは話していないが、朝方やっと帰ってきて泥のように眠る彼に対して既にこの口調である。ちなみにまだ一緒に暮らし始めて一週間だ。だが、今まで誰にも束縛されることなく自由に暮らしてきたメローネにはこれくらいの小言がかえって新鮮で心地よかった。
今までメンバーとのアジトでの生活以外に誰かと暮らすという経験の無かったメローネに対して、女の方は何度か同棲の経験があるらしい。掃除洗濯をし、栄養も彩りも完璧な料理を作り、メローネの世話を焼いた。
いつ帰っても清潔で暖かい部屋が待っているという生活は、分かりやすくメローネを幸せにした。美味しい料理のおかげか、ここ数日体調も良い。このままでは、とメローネは考えた。
「まずいな…」
えっ、と女が顔を上げる。いつものように二人でテーブルを挟んで夕食をとっている時だった。今日はメローネのリクエストでアクアパッツァを作ったのだ。ちなみに買い出しはメローネが全て行っている。女は理由こそ話さないが、命を狙われているということで外出はもちろん、窓に近づくことすらしない。今夜の食材もメローネが朝一でメルカートに行って選んできた。
「ごめんなさい。美味しくなかったかしら…」
女が不安そうに聞いてくる。自分の失言に気づいたメローネが慌てて訂正をする。
「いや、君の料理がまずいと言ったんじゃあ無いんだ。ごめん、ちょっと考え事をしていてね。うん。このアクアパッツァは最高だよ。いんげんのスープも人参のサラダも最高さ」
これは決して大袈裟な表現では無い。今夜のメニューはどれも素晴らしく美味しく、良かったと笑う彼女と一緒に食べ過ぎで動けなくなるまで夕食を楽しんだ。
+++
メローネと名乗る男は一体何を考えているのだろう。彼のおかげで両脚の傷も治り、体力も回復した。外に出ないのは自分の意思だが、欲しいものがあると言えばどんな物だって買ってきてくれる。この部屋も自由に使うことを許されているどころか、大きくて寝心地の良いベッドは初日からずっと私に使わせてくれている。彼はパーテーションで仕切ったリビングのソファで眠るが、一度だって私の眠るベッドに入って来たことは無い。
これは素直に好意として受け取りたい。もしかしたら今まで出会ってきた男たちと同じように何か企みがあっての事かもしれないが、彼に対してだけはそんな疑いを持って接したくは無い。これから自分がどうやって生きていくのかすら分からないこの状況で、今はただ彼の優しさだけを信じてそれに応えていこうと思う。
+++
任務が終わってマンションに戻る事を楽しみにしている自分がいる。アジトに向かう回数が必要最小限になった代わりにメルカートやスーパーで食材を吟味する時間が増えた。長期任務の後にはその土地で土産を選ぶ。常に彼女の事を思っている。
もう手遅れなんじゃあ無いかとメローネは考えた。自分の中の変化はとっくに自覚していた。少し一人になった方が良いと判断して、今日は朝からアジトの自室に籠っている。
彼女を拾ったのは単なる好奇心だった。ベイビィの母体になるかもしれない。女という生き物を観察してみるのも面白そうだ。そこそこ使えそうなら、あるいはとんでもなく使い物にならなかったら、組織に渡せば何かしらの道具にはなるだろう。それくらいの事しか考えなかった。なんとなく珍しいものが落ちていたので拾ってみた。それだけの事だった。
しかし今は。
もしかしたら自分では気づいていなかっただけで、端からこういう関係を望んでいたのかもしれない。彼女を、好きになってしまった。
彼女に手を出さなかったのはそれで恋人気取りをされたら面倒だと思ったからだ。だがいつからか、好きだからこそ大切にしたくて守ってやりたくて、彼女の眠るベッドに近づくことが躊躇われるようになっていた。
なんでも買い与えていたのは彼女が財布を盗んだり他所で万引きをしたりするのを懸念してだった。だが、今では彼女に喜んでもらいたくて物を買ってやっている。もちろん生活に必要なものしか強請られたことはないが、その日常的な買い物がたまらなく楽しい。
身元の分からない女を拾うことに抵抗はなかったが、さすがに恋愛感情をもってしまってはいけないという意識はあった。そうならない自信もあった。が、彼女との生活が自分の体に馴染んでいくにつれ、気づかないうちにその心までも絆されてしまっていたようだ。
彼女を失うのが怖い。
この感情が一番危ない。メローネは暗殺者だ。数えきれないほどの人間を殺し、それ以上の数の人間から命を狙われるほど恨まれている。常に己の命を危険に晒している状態で、この感情は邪魔なものでしかない。
これ以上抑えきれなくなる前に彼女と別れなくては。
そう結論に達して、しかしどうしても苦しくて一人で顔を歪めていると、扉をノックしながらリゾットが声を掛けてきた。
「メローネ、次の任務が決まったから報告がしたい。入るぞ?」
そう言って渡された報告書をパラパラと捲って、メローネは息を飲んだ。
+++
今朝、メローネはちょっと用事があるとだけ言って出かけていった。帰りはいつになるかわからないから、食事はいらないらしい。そうなると掃除と洗濯を終えたあとは、私は時間を持て余してしまう。
メローネがいつも寝ているソファに座りながらぼんやりと部屋を見渡していたら、ふとここに来る前の事が思い出された。嫌な記憶だが、何故か止まらずに溢れてくる。私は男と一緒に暮らしていた。
男と暮らしたのは半年間だった。暮らし始めて二ヶ月目にギャングの構成員だと打ち明けられた。三ヶ月目に組織の薬を横領していると聞かされ、四ヶ月目にはそれを手伝わされた。五ヶ月目に横領した薬に二人で手を出してしまい、六ヶ月目のその日、私の目の前で男は殺された。
向けられた銃口からはまだ硝煙がかすかに上り、火薬の臭いが辺りに漂う。目の前にいる相手が組織の人間であること、薬の横領がバレて男が始末されたこと、そして今から私も男と同じ目に遭うことを、瞬時に理解して覚悟する。もう動かない男を挟んで銃口を向ける相手と向かい合う。死ぬと分かったら、不思議と恐怖も後悔も感じなかった。いや、一つだけ。今の私はシャワーを浴びたばかりで身に着けているのはバスタオル一枚だ。身体を見られるのは気にならないが、こんな恰好で死ぬのは少し滑稽だ。
カチャリと撃鉄を起こす音が聞こえる。いよいよだ。男と私の死体はどうなるのだろう。小説や映画みたいに海に捨てたりするのだろうか。
が、結局私は死ななかった。まさかというタイミングで雷が落ち、マンションが停電したのだ。考えるより早く、死体を飛び越えて男に体当たりをし、私は走り出した。ここは私の部屋だ。真っ暗でも玄関の位置と距離くらいは分かる。私たちを始末しにきた男は不意打ちを食らったのと真っ暗闇なのとで慌てたらしく数発の発砲音をさせていたが、すぐに追いつかれることは無かった。
私はそのまま無我夢中で走り続け、あの場所にたどり着いたのだった。
扉が開く音で目が覚める、いつの間にか眠ってしまっていたようだ。身体を起こすと、メローネが入り口に立ってこちらを見ていた。
「おかえりなさい。眠ってしまっていたみたい。何か飲む?食事は?用意するわ」
そう言って立ち上がろうとする私をメローネが止める。
「食事はいい。…逃げて、くれないか」
彼がゆっくりと近づいてくる。苦しそうな表情の彼を初めて見た。右手を上げ、私の頬に触れる。彼の手はこんなにも温かかっただろうか。そのまま腰に腕を回され、強く抱きしめられた。
「愛してる」
温かい。彼の体は微かに震えている。
「君を愛している。守ってやりたい。だから、お願いだ。ここから、俺のもとから逃げてくれ」
私は何と言っていいのか分からず、彼の体に腕を回すこともせずに黙っていた。
きっと私の追われていた理由を知ってしまったのだろう。いつかはこの日が来ると思っていた。覚悟もしていた。ただ、こんなにも悲しい気持ちになるなんて知らなかった。
「…分かったわ。今まで、ありがとう」
身体を離し、彼の目を見ながら伝える。苦しそうな表情の中で、少しだけ彼が笑ったように見えた。
「最後に…」
彼の顔が近づいてきた。私はそっと目を閉じる。重なった唇は温かくて優しかった。首の後ろがチクリと痛んだ気がしたが、そんなことはすぐに気にならなくなっていった。
+++
逃げてくれ。どうか俺から逃げてくれ。俺のスタンドは最強だ。無敵の遠隔型スタンドだ。君の血液を採取した。これでベイビィ・フェイスはターゲットである君をどこまでも追跡する。逃げられる筈が無いんだ。だが、お願いだ。どうか君だけは逃げてくれ。俺にこの任務を失敗させてくれ。
リゾットの言葉が頭の中で響いている。
『今回のターゲットは組織の薬に手を出した女だ。麻薬チームの一人が始末しに行ったが逃げられてな。俺たちに指示がきた』
『女の所在は不明だ。悪いが探し出すところから始めなくていけない。居場所さえわかれば接触をして血液を採取。そこからはお前のスタンドなら、たとえ女が逃げていっても大丈夫だろう』
あぁ、大丈夫さ。俺のベイビィなら確実に仕留めるさ。女の居場所だって、血液を採取することだって、何も問題は無いよ。任せてよ、すぐに終了の報告を入れてやるぜ。絶対に逃げられないんだ。でも、守ってやりたかった。
ほら、ベイビィからメッセージが来たよ。
ターゲットを始末しました。これから帰ります。
完