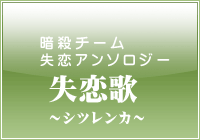それは別にどうってこともない、見慣れたただの「背景」だった。
バールにて by明日狩り
アジトの一階に入っているリストランテはそれなりに味も良いし、何より近いので暗殺チームのメンバーも毎日通っている。けれども「職場」に近すぎるというのもそれはそれで味気ないもので、他に行きつけの店を持っている場合も多い。
ギアッチョも食べ物の味にはうるさいほうで、お気に入りの店はいくつもある。感じが良いのでつい行きたくなってしまう店。財布が厳しいときに利用する店。高いけれど特別の日に行きたい店。知り合いとわいわいやりたいときに使う店。一人で静かに時間を過ごすための店。けれどもそういう「選択肢」の中の店とは違っているのが、街角にあるそのバール(喫茶店)だった。
「ちわー」
いつものように入っていくと、彼女がいつもの笑顔で「チャオ! ギアッチョ!」と言った。金髪を後ろでポニーテールに結い、緩いウェーブをいつでもヒラヒラさせているカメリエーラ(ウェイトレス)だ。年齢はギアッチョと同じくらいか。
「おう」
入り口で会計を済ませ、カウンターで商品を待つ。彼女は店の奥のテーブル席へスパゲッティを届けると、カウンターへ小走りに近寄って来た。
「昨日のテレビ見た? アンタの好きなバンド出てたじゃない」
「あー、新譜のPV発表だろ。あれイマイチじゃねえ?」
「そう? 私は好きだけど」
そんな短い会話を交わしている間に、エスプレッソが出て来る。ギアッチョはそれに砂糖を二つ入れ、ガリガリと乱暴にかき混ぜると一息に飲み干した。まだ溶け残った砂糖がカップの底に残っているのも構わずに、「グラッツェ」と言って店を出る。
「またね!」
「おう」
その間、およそ二分。これがギアッチョの毎日の決まりだ。一日に一回、もしくは二回。このごくありきたりなバールでエスプレッソを飲むことが、ギアッチョの生活の一部になっている。
別にこの店を特に気に入っているというわけでもなく、ただ自宅からアジトへの間にあって便利だというのが一番の理由だった。価格は普通か、やや安いくらい。味は普通。サービスも普通。だから行きつけにする理由もないし、自分がこの店を行きつけにしているという意識すら特になかった。家から職場に向かう際の一服。それがいつの間にか習慣化しているだけで、この店に思い入れもない。
店員にしたってそうだ。よく話しかけてくる明るい金髪と、おそらく店主の妻であろう中年女性の二人。カウンターにいるのがバールマスターの店主。たった三人でやっている店だが、ギアッチョは彼らの名前すら知らなかった。前に常連客が何か名前を呼んでいたのを聞いたことはあるが、覚えていない。そのくせ金髪の若いカメリエーラはなぜかギアッチョの名前を知っていて、店に行くたびに必ずひと言は会話を交わす。
「チャオ、いらっしゃい」
「エスプレッソ」
「いつものね。あ、昨日はサッカー勝ったね!」
「あったりまえだろ。あんな相手に負けるわけねぇ」
「でもけっこう危ないシーンがあったじゃない。後半残り五分でさ」
「あんなのは見せ場作ってやっただけだろうぜ。……ごちそうさん」
「またね、ギアッチョ!」
「いらっしゃい、今日は遅かったのね」
「悪ィ、もう店閉めるか?」
「エスプレッソ一杯くらい、どうとでもなるわ。ねえマスター?」
そう言っている間にもうマスターはエスプレッソマシンにカップを準備している。それを横目に見て彼女は得意げに笑う。
「ほらね?」
「おう」
「家、近くなの?」
「そりゃそうだろ。近いから来てンだよ」
「だろうと思った。なら安心ね」
「何が安心だよ。オメーこそ気をつけて帰れよ」
「グラッツェ、ギアッチョ。おやすみなさい。またね」
毎日、毎日、朝、昼、晩。
たまにはシゴトの都合で行けないこともあるが、それで生活のリズムが崩れるだとか気持ちが悪いだとかいうこともない。ただ行けるときは行き、エスプレッソを飲み干して去る。そういう「儀式」のようなものが、ギアッチョはそれなりに気に入っていた。
そして、ある日の朝。
「……ん?」
いつものようにあの店に行くと、彼女がいなかった。
「エスプレッソ」
「はい」
寡黙なマスターが商品を用意している間、ギアッチョは奇妙な沈黙に居心地の悪さを感じる。たかがエスプレッソ一杯を抽出する時間などたいしたことはないのだが、この時間がやけに長く感じられるのは、あのおしゃべりな金髪のカメリエーラがいないせいだ。
(あいつ、いっつも話しかけてくるもんな。すげーおしゃべりだしよ)
そういえば、この店に来るときはいつも必ず彼女が話しかけてきた。生来のおしゃべり好きもあるのだろうが、常連客へのお愛想もあったのだろう。
出て来たエスプレッソに砂糖をふたつ入れ、乱暴にかき混ぜて一息に飲み干す。
「ごちそうさん」
マスターは目だけで「グラッツェ」を示し、ギアッチョはそのまま店を出た。
翌朝も、彼女はいなかった。
「エスプレッソ」
「はい」
そして沈黙。店内を見渡すと、テーブル席で軽食を食べている老人が一人。手帳に何かを書きつけている男が一人。カウンターに寄りかかってじっと何か考えている男が一人。店の中はしんと静まりかえっていて、エスプレッソマシンの音がやけに大きく響く。
(こんな店だったか?)
賑やかな店だと思っていたのに、こういう日もあるのかも知れない。素早く提供されたエスプレッソに砂糖をふたつ入れ、飲み干してギアッチョは店を後にした。
翌朝も行った。
「エスプレッソ」
「はい」
彼女はいなかった。どうかしたんだろうか、と思う。
その日は夜にも寄った。
「エスプレッソ」
「はい」
彼女はいなかった。店を辞めたんだろうか。そんな気がする。
翌朝も、彼女はいなかった。その日は昼にも近くを通りがかるついでに寄った。夜、自宅へ帰る時にも入った。いつ行っても、彼女はいなかった。きっと辞めたのだろう。若いアルバイトがいつまでも店にいることの方が珍しい。
翌朝、カウンターで金を払いながら、ギアッチョはマスターに声を掛けた。
「エスプレッソ。……あのよぉ」
「はい?」
「………………いや、別に」
何となく、聞けなかった。いや、聞こうとしたけれども聞けなかったのだ。何しろギアッチョはあの子の名前すら知らない。『あの金髪のカメリエーラ』と言えば確実に通じるだろうが、そんな言い方で彼女のプライベートな事情を聞き出すのは分不相応な気がした。それに、これだけ毎日通っていたくせに彼女の名前すら知らなかった自分が何となく恥ずかしい。
「どうぞ」
エスプレッソが出て来る。砂糖をふたつ入れ、ゆっくりかき混ぜて、溶けていく砂糖を見ながらギアッチョはそんなことをぼんやり考えていた。
「そういえばよ、あそこのバール。ほら、通りの角にある店、行ったことあるか?」
アジトのリビングで酒を飲んでいる時、話の弾みでふとホルマジオがそんなことを言った。ギアッチョはなぜかそれを聞いたときギクッとして身を強ばらせたが、プロシュートが煙草の煙を吐きながら先に返事をする。
「あー? ……ああ、そういやあったなァ。あそこバールか。地味すぎて記憶にねぇわ。確かにあったあった」
「そうそう、あの地味なバール。小さくてよ。家族三人でやってた店」
(家族だったのか)
それを聞いて初めて、あの三人が家族だったことを知った。ギアッチョが驚きを隠して黙っていると、プロシュートとホルマジオが勝手に会話を進める。
「お前よく知ってんな。行きつけだったのか?」
「いやいや、何度か行っただけ。あそこ飯まずくてよォ」
そう言ってホルマジオは顔をしかめた。
「じゃあ何だよ」
「いや、それがよ。あそこに若いカメリエーラがいたんだよ。覚えてっか?」
「知らねぇ。入ったことねーし」
「ブロンドだったか、茶色だったか忘れたけど、愛想の良い子。顔はあんまよくなかったけど」
ホルマジオがちょいちょい低い評価をするので、ギアッチョはイライラしながら聞いていた。だが余計な口を挟む気はしない。黙って興味のないふりをしながら、二人のやり取りを聞いている。
「その娘ってのがよォ、どうも死んだらしいんだ」
「えっ…………」
思わず声に出してしまい、ホルマジオが「ん?」という顔をする。
「ギアッチョ、お前は知ってんの?」
「あ、いや。知らねえけど」
とっさに嘘をついてしまった。なぜ嘘をついたのかは自分でも分からない。ホルマジオは特に気にした様子もなく話を続けた。
「それがさ、面白ぇんだ。うちの『組織』の入団試験を受けたらしいぜ」
「へー。なんでまた」
「それは知らねーんだけどさ。ほら、うちのポルポのさ。例のアレがあるじゃん」
そう言ってホルマジオは自分の心臓をちくちくと指先でつつく真似をした。「ポルポの矢の試験」の話は有名で、試験に合格すれば『組織』への入団が許され、しかもスタンド能力を身につけることが出来る。だがそれはかなりの狭き門だという噂で、たいていの生半可な挑戦者は死んで終わりだということだ。
「あー…………で、失敗したわけか」
「そうそう。つーかそんなふうには見えなかったんだけどなァ。ごく普通の女の子だったぜ」
「何かあったんだろ。人は見た目じゃ分からねぇ」
「まーなぁ」
二人はそれほど興味があるわけでもないようだったが、ギアッチョは目をそらして胸の動悸を押さえるのに精いっぱいだった。
(なんで……なんでアイツが……そんなこと…………?)
ギャングと関わりがある様子は一切なかった。毎日ほんの他愛のない会話を交わす程度だったが、その話はいつでもテレビやら天気やら、ごく一般的な内容しかなかった。ごく普通のバールで働く、どこにでもいるごく普通の若い娘。あの子がギャングの入団試験を受ける、なんていうことは想像もつかない。
何か、あったのかもしれない。客とのトラブルか、あるいは客にそそのかされたか。もしくはあのマスター? それともおかみさん? 学校の友達? いや、毎日店にいたから、よく考えたら彼女は学校へも行っていなかった。それもおかしな話だ。それとも見かけほど若くなかったのかもしれない。そういう可能性だってありうる。
こうして改めて考えると、ギアッチョは彼女のことを何一つ知らなかった。毎日、毎日、あんなに話をしていたのに。あんなに顔を見ていたのに。ひょっとしたら暗殺チームの仲間よりもずっと顔を合わせる頻度は高かったかもしれない。それなのにギアッチョは、彼女の名前も、年齢も、家族で店をやっていたことも、何も知らなかった。
(まあ……いいんだけどよ……)
特別な感情があったなら、話しかけていただろう。そうしなかったということは、彼女はギアッチョにとってただの店員だ。たとえ毎日会っていたとしても、店員以外の何者でもなく、いなくなったらそれだけの存在に過ぎない。
それなのに、この気持ちはなんだろう。
翌日、またあの店へ行った。
「エスプレッソ」
「はい」
いつもの手順で金を払い、いつものタイミングでエスプレッソが出て来る。店内は相変わらず、火が消えたように静かだ。そういえば娘が死んだというのに、店が休業した様子もない。葬式はどうしたのだろう。普通は何日か店を休んで葬式を出すものだ。それなのにギアッチョが疑問を感じる余地もないほど、店はいつも通りに営業していた。そもそもホルマジオが言っていたことは本当なのだろうか? ただの噂かもしれないし、別の店の話だったかもしれない。いや、角の店で親子三人でやっているバールなんてそう多くはない。おそらくここで間違いないはずだ。彼女がいない店。彼女がいたときの店。最後に話した言葉は何だったろう…………?
頭の中を思考がぐるぐると回る。白く小さなカップを手に取り、砂糖を入れ忘れたことにも気付かないまま、ギアッチョは苦いエスプレッソを飲み干した。ぼんやりと宙を見つめ、何の音も聞こえなくなる。
「……………………」
ごちそうさま、も言わずにギアッチョは店を出た。一歩、二歩、三歩……。店から遠ざかる。そうしてふと、思い出した。
最後に彼女の口から聞いたのは、いつものひと言だった。
「ギアッチョ、またね」
完