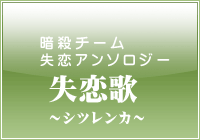こうして一緒にいられるのは、久し振りだね。
パーティ・ナイト by明日狩り
※注意・若干のグロ表現を含みます※
「乾杯。……ふふっ、君のためにとっておきのお酒、買ってきたんだ。お店でもなかなか入荷できないっていうレアもののワイン。オレはワインとか飲まないんだけど、これは美味しいんだって」
「そんな顔するの止めてよォ。ごめんね? 最近全然会えなかったもんね。でも今夜は君と一緒だよ。このワインだって君のために買ってきたんだもの。ね、機嫌直してよ」
「ブルスケッタ、おいしいよ。完熟トマトのカプレーゼも、君の好きなアラビアータも作ったよ。ほら、食べようよ」
「なんでそんなに怒ってるの? 泣いてるの?」
「…………う、うん。そうなんだけどさぁ。ごめん。ごめんってばぁ。そうだよ。確かにこのワインはソルベのために買ったの。それは本当。でも聞いてよ! 怒らないでってばぁ」
「ソルベったらひどいんだよ。オレ、確かにソルベのことは好きだけど、そういう意味の『好き』じゃあなくてさ。ただ同僚で世話してるだけっていうか、ちょっと問題がある人だからオレが一緒にいないとダメっていうか、チームでも二人一組でシゴトしてるし、確かに一緒にいるんだけど。でも別に変な意味で好きなわけじゃないしね? デキてないしね? それは君も分かってくれてるよね?」
「そうだよ! デキてないってば! 君も分かってくれてると思ったのに……残念だなぁ。じゃあこの機会にちゃんと誤解を解いておくよ。オレとソルベはデキてない! それだけは確かだよ。ね、だからオレを信じてよ」
「うん、まあ、そうなんだけど。そのソルベのために買ったワインだけどー……。だってソルベったら、お酒がないと暴れるんだもん。しょうがないじゃん。おとなしくしてもらうためにはしょうがないの。そのソルベがここ最近手が付けらんない状態で、だから君とも会えなかったんだよ〜。ね、許して?」
「シゴトの一環だよ、お仕事。これもお仕事。ね、君なら分かってくれるよね? ソルベったら酒と煙草とたまにオクスリがないとすぐ暴れたりするから、オレも大変なんだって。せっかく君と仲良くなってきたっていうのに、なかなか会いに来れなかったし、とても寂しかったんだよ?」
「ずっと放って置いて悪かったって。ねえ、怒らないで? わざとじゃないんだ。ソルベが全然、離してくれなかったんだもの」
「ソルベったら、オレに新しい恋人ができたこと、ひょっとして分かっててやってたのかな? ううん、その筈はないんだけどなぁ。オレはソルベのことは何でも分かるけど、ソルベはオレのやることなんて何にも気にしないし、なんだったらオレのことなんて何一つ知らないよ。そんなソルベが、オレに嫌がらせ? まさかね」
「オレだって君と一緒にいたかったよ。だって君とはようやく仲良くなれたばかりじゃない? その矢先に放っておくんじゃ、好かれなくても仕方ないよね。ううん、君の気持ちを疑ってるわけじゃないんだよ。君はずっとオレのこと、心待ちにしててくれたもんね? 知ってるよ」
「そうだよ。よく分かってるよ。君がオレに会いたいってずーっと思っててくれたこと、ちゃんと分かってたからね。うん、ごめん。分かってたけど、来れなかった。それは本当に謝るよ。ごめんね? 心から許して欲しいんだ」
「だからさ! ほら、こうして、良いワインを持ってきたでしょう。もうソルベになんかあげるか!って思って、君に持ってきたんだよ? だってあの飲んだくれ、何飲ませたって同じなんだもん。今度工業用アルコールでも飲ませてやろうかな?」
「ごめんごめん、ソルベの話ばっかりだね。だってずっと会いに来られなかった理由を、ちゃんと説明しておかなきゃでしょ? 君は疑り深いし、オレの話をあんまりちゃんと聞いてくれないし、だけどこれだけは分かってもらわなきゃいけないんだもん。ちゃんと聞いてよね?」
「聞こえてる? オレの言うこと、ちゃんと聞いてる?」
「ごめんごめん、そんなに泣かないでよ。分かったよ、もうソルベの話はしない。それでいいでしょう? オレはずっと、君に会いたかったの。でも来られなかったの。それを分かってくれればいいよ」
「うーん、まいったなぁ。そんなに泣かないでよ。寂しがらせちゃったのは本当に悪かったって思ってる。オレに会いたくて会いたくて、仕方なかったんだよね? オレだって君に会いたかったよ」
「うん? 何? 良く聞こえない」
「ああ、そうなんだ」
「そうなのか………………」
「ごめんね。……ごめんね、って言っても、許してくれない?」
「ごめんなさい」
「………………………………」
「……………………ごめんね………………ほんとごめん…………」
「もう無理なのかな」
「ごめん。オレにはそれしか言えないよ。だって……ってもう、言い訳するのもやめようか。オレが君を放って置いた事実はもう変えられないんだもんね。過去は変えられない。謝ることしか……できないよ……」
「ごめんなさい」
「会えなくてごめんね」
「そんなにオレに会いたかったんだね。オレもだよ」
「うん、もう遅いんだね」
「手遅れ………………みたいだね」
「ごめんね、本当に。こんなつもりじゃなかったんだ」
「もっと君のそばにいるつもりだったんだ。わざとじゃないんだよ」
「そう。毎日君と一緒にいて、ご飯を食べたり、テレビを見たり、楽しい時間をいっぱいいっぱい、一緒に過ごすつもりだったんだ。本当にそうなると思ってたんだ。オレは君のこと大好きなんだもの。君だってこんなにもオレに会いたがってくれてたでしょう? そのこと、オレはちゃんと知ってたんだよ」
「忘れてたわけじゃないんだ。本当に。二の次にしてたつもりもないんだよ。しょうがなかったんだ。しょうがなかったんだよ」
「……もう………………遅いのかな……」
「やり直せない?」
「もう、無理?」
「ねえ、本当に無理なの?」
「そんなの、演技でしょ? 本当は君だってもう一度やり直したいって思ってるんだよね? だからわざとそんなふうに、オレに冷たくするんでしょう? ねえ、それ、演技だよね?」
「オレ、信じないよ。だって信じたくないもの。あんなに明るくて元気だった君が、そんな風に静かに泣いてるだけだなんて。嘘みたいだよ。だから嘘なんだよね?」
「嘘だよ、きっと嘘。そんな弱々しい君なんて嘘に決まってる。演技だよね? オレのこと、責めてるんだよね? オレが君のこと放って置いたから、怒ってるんでしょう? 復讐のつもり? そんなの、全然君らしくないよ!」
「…………ごめん、言い過ぎた。そうだよね。君が元気ないのは分かってる。でも……君とお別れだなんて……そんなの信じたくないんだもん……」
「ねえ、お願いだよ。元気出してよ。元気のない君なんて見たくないよ」
「だってあんなに元気だったじゃない。元気が君の取り柄だったよね? 太陽みたいに明るくて、はつらつとして健康的で、お母さんのことが大嫌いだって爆弾みたいに怒り狂ってたじゃない。オレ、覚えてるよ。あんまりすさまじい怒り方だったから、すごい子だなぁ〜って思って聞いてたんだ」
「違う違う、嫌いなんじゃないよ。オレ、君みたいな子、好きだよ。自分の気持ちに素直で、それをちゃんとまっすぐ表現できる子。好きなんだ。それに母親らしくない母親って境遇もオレと同じだったから、すごく同情したよ。だからこうして、家出した君に住む場所を提供してあげたじゃない。喜んでくれたよね?」
「ありがとう、って。君に言われたの嬉しかったなぁ。もう独り立ちしてもいい年だし、お母さんなんかに頼らなくても生きていけるんだから、ここにいれば良いよって。そう言ったら君、すごく喜んでたじゃない。オレも嬉しかったよ」
「思い出すなぁ。君との生活が始まったばかりのあの頃。ずっと一緒にいたよね。ほらオレ、尽くすタイプじゃない? 誰かの世話を焼くのって全然苦にならないんだよね。お母さんの悪口を言いながら一緒にパスタを食べたよね。あのときオレが作ったアラビアータ、おいしいって言ってくれたよね」
「すごく楽しかったよね」
「君がいる生活、とても楽しくて。オレも嬉しくて。仕事から帰って家に君がいてくれるのはすごく心が温まったよ。幸せな気持ちだった。君だってそうでしょう?」
「オレに出逢えて良かった、って言ってくれたよね」
「どうして君、あんなことしたの?」
「ご飯だって、君が食べたいっていうものを作ってあげたのに。欲しいって言うから、バッグだって靴だって買ってあげたじゃない」
「それなのに、どうして」
「どうして、あんなことをしたの」
「ねえ、教えてよ」
「黙ってないで」
「どうして」
「逃げだそうとしたの?」
「お母さんのところから逃げて来たのに、また逃げようとするなんて。意味が全然分からないよね。自分でも何をしているか、分からなかったのかなぁ?」
「君は一体、何から逃げたかったの? 自分が恐かったのかな? 第一、逃げる相手を間違えているよね。お母さんのことは大嫌いで、そこから逃げて来たんでしょう? せっかく逃げ込んだオレの家からもまた逃げようとするなんて、おかしいと思わない?」
「君は混乱していたんだよね。オレのこと、好きでしょう? 逃げ出すなんてどうかしてたんだ」
「だってほら、君、さっきはちゃんと言ってたじゃない。『どうして帰ってきてくれなかったの?』って。『ずっと待ってたのに』って。口で言わなくても分かるよ。君の心は全部分かっちゃうんだから」
「待たせたのは悪かったよ。だけど最初に逃げだそうとした君はもっと悪いよ。だってオレの心を踏みにじったんだもん。だから、仕方ないでしょう?」
「ねえ、聞いてる? 聞いてるの? さっきから何も言わないけど。怒ってるの? 泣いてるの?」
「ねえ、オレの言うこと、ちゃんと聞いてる?」
「聞こえてる?」
「聞こえてないの?」
「放って置いて、ごめんね」
「長すぎたよね」
「泣かないで」
「お願い、本当に悪かったって思ってるんだ。だから、泣かないで」
「お願い、泣かないで」
「恐いの?」
「もう大丈夫だよ。オレ、ここにいるよ?」
「ねえ、何とか言ってよ」
「もう放っておかないよ。ちゃんとご飯も作る。お金なんかいらないんだ。君はここにいてくれるだけでいい。今までみたいにね。君に何も負担は掛けない」
「ちゃんとご飯、作ってあげるからさ。許してよ」
「うん、ちゃんとやるよ」
「ご飯、作ってあげる。ワインも飲ませてあげる。水? 水だって飲ませてあげるよ」
「喉が渇いたの?」
「そうだね、水道まで届かなかったね。鎖、短すぎたね」
「冷蔵庫も届かなかったもんね。喉が渇いてたのか。そうだよね。ごめんね」
「うん、トイレに行けないのは知ってた。だけどすぐ帰ってくるつもりだったから」
「だから別に恥ずかしがることないんだよ。こんなに垂れ流してても、それはオレが悪いんだから。君はなんにも恥じることないんだ。自然の摂理だもの。生理現象は止められないんだから」
「君のこと、汚いなんて思ってないよ。君は今でもすごく綺麗で、キュートだよ」
「君を鎖に繋ぐつもりなんてなかったんだよ。だけど君が逃げるから」
「それにこんなに長い間、放っておくつもりだってなかったんだ」
「ねえ、聞いてる? オレの言うこと、聞こえてる?」
「水が飲みたいの?」
「ご飯が食べたいの?」
「トイレに行きたい?」
「ほら、ワインがあるよ。上等のだよ。それにご飯も作ってあげた。食べようよ」
「どうして黙ってるの?」
「水……飲みたいの?」
「ねえ、何とか言ってよ」
「黙ってないで」
「さっきから君、ずっと黙ってるね」
「ねえ、何か言ってよ」
「…………オレたち、もう、終わりなの?」
「これでお別れなの?」
「大好きなんだよ。今でもずっと、君のことが大好きなんだよ」
「…………もう、聞こえてないのかな」
「ごめんね、こんなつもりじゃなかったんだ」
「うん、言い訳してもだめだよね。君はもう、帰って来ないんだね」
「手遅れだったんだ。すべて、何もかもが、遅かったんだ……」
「もう……お別れ、なんだね」
「寂しいよ」
「とても、とても、悲しいよ」
「もう一度、君と話し合いたかった。でももう君は、何も言わない」
「何も言えなくなってしまった」
「ごめんね」
「さようなら」
「さようなら」
「大好きだったよ。さようなら」
ジェラートは立ち上がり、涙を拭った。すさまじい臭気を放つ室内を見回し、衰弱して完全に沈黙したかつての恋人を悲しそうに見下ろす。
「……やっぱりオレには、ソルベしかいないのかな」
ぽつり、とつぶやいたその言葉は、かつての恋人の耳には届かない。
完