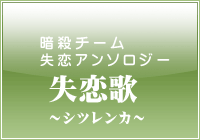平凡でありきたりな思い出すら、愛おしく懐かしい。
ひどく退屈でありきたりな恋愛 byジュリエッタ・S・リュンヌ
真夜中の路地に一人、ターゲットを待ち伏せる。
「ったく、いつまでお楽しみなんだよ。」
見張り役のメローネが電話口で愚痴る。
「ホルマジオ、さっさと終わらせてくれよ。寒いし、腹減った。」
「しょうがねぇなあ。まあ、そんな時間は掛からねえよ。で、奴のナニを切り取って咥えさせときゃいいんだっけ?」
「それはやらなくっていいってさ。ボスは下ネタがお嫌いらしい。代わりに目玉握らせろだって。」
「ちっ、面倒くせえなあ。了解。じゃ、また後で。」
重さの欠片もない会話。だがこれから俺達がする「仕事」は「人殺し」だ。
今日のターゲットは上納金を払うのを渋った小物のギャングだ。スタンド使いでもない。情婦の部屋からの帰り道をメローネが見張って、俺が待ち伏せて、ナイフで刺し殺す。明朝死体が発見されると、善良な市民は眉を顰め、同業者はパッショーネの制裁に震え上がるという寸法だ。
俺はナイフの手触りを確かめた。相手が同類でもない限りスタンドは使わない。使ったとしてもあくまで補助的にだ。変に謎を残して好奇心の強い輩に首を突っ込まれるのも面倒だし、同業者に能力のヒントは与えない方がいい。結局トドメを刺すのは自分の手だ。
人を殺すのが俺の仕事で、日常。
「寒ぃ。」
空を見上げれば星が綺麗だ。そういえばこんな夜は「星よりもお前の瞳の方が綺麗だ」とかなんとか歯の浮くような台詞で女を口説いては楽しんでいた頃もあったっけ。まだ喧嘩と盗みだけで世の中を渡っていた時期だ。
そういえば誰だったか、もう顔もはっきりと思い出せない。ただその居心地の良さだけが記憶の底に残っている。
特に美人でも体が良いわけでもない、可もなく不可もなく何人かの集団の中では一番俺の好みにあっていたというだけの女。出会った季節さえ曖昧だ。何ヶ月付き合ったっけ。ナターレは玄人の別の女と過ごしていたから二、三ヶ月かもっと短かったかも知れない。
確かエリートには程遠いけれど売女よりはマシというレベルの学生で、女数人で飲んでいたところを仲間とナンパした。尻軽な節操のなさを自由奔放とはき違えた女達はそれぞれの男と並んで夜の町に消え、ご多分に漏れず俺もその夜のうちに彼女をいただいた。
顔も体も普通。何をどう色々やったのかは覚えていないが、彼女の反応が意外に初心だったのが印象的だった。遊んでいるふりはしているが口だけの素人だったと思う。
「彼氏いねぇの? だったら俺と付き合わねえ?」
半分はヤっちまった女への挨拶みたいなもんだが、丁度彼女もいなかったし彼女がOKを出してくれたのはラッキーだった。少なくともこれからは出かけるにもそこそこ可愛い女を連れて歩けるし、何より男にとっては夜を一緒のベッドで過ごせる相手が必要だ。
女にしたって悪くて(自分で言うのもなんだが)ちょっといい男と付き合って、遊んでる風を装っては周りの女を羨ましがらせる事が出来る。自分に絡んで来たうっとおしい男を強面の彼氏がおっぱらってくれれば安いドラマのヒロイン気分も味わえる。
恋愛感情なんて後回し、ノリと勢いと利害の一致でインスタントなカップルが出来上がる。
連絡先を交換して、一緒に映画を見たり買い物をしたりした後に部屋でセックスをする。金のない若いカップルのデートの中でも最もシンプルな方法でダラダラと休日を過ごす。彼女はのべつ幕無し自分の事を話していたような気がするが内容なんてこれっぽっちも覚えていない。お互い自分勝手な話をして会話なんて成り立っていなかったのに笑ったり不機嫌になったりしていた。
そんな関係なんて飽きがきて当然だ。別れはすぐにやって来る。理由も俺の浮気という何の変哲もないものだった。
お互いに飽きていた俺達の気持ちはささくれ立ち、会えばくだらない事で喧嘩になる事が増えてきていた。その何度目か、キレた彼女が出て行ったのをいいことに俺は仲間と一緒に町へ繰り出し、また女に甘い言葉を投げかけて部屋に連れ込んで楽しんだ。楽しんだつもりだったが女は連絡先も教えてくれなかったし、また会おうと言ったら体よく笑顔で誤摩化された。俺は随分良かったが、向こうにはご満足いただけなかったらしい。
まあ、こんな日もあるさと酒と煙草で気を紛らわせていると彼女が帰ってきた。不機嫌極まりない顔でクンクンと辺りを嗅ぐと、俺に向かって女を連れ込んだだろうと言う。しらばっくれようと思ったが、浮気相手の香水の匂いがしっかりベッドのシーツに染み込んでいた。
あんたって最低、と彼女は俺を睨みつけたが、今更どうでもいい俺は面倒臭くて形ばかりの言い訳をした。後はお決まりのパターン、俺の欠点をあげつらいながら別れると言う彼女に返事もせず、出て行く後ろ姿を引き止めもせず、音信不通になってそれっきり。別れの言葉もなく、俺達は別れた事になった。
「喧嘩をしている最中に彼氏が浮気してムカついて別れた」
言葉にすればどこにでもありすぎる。お節介な仲間が、彼女には別れる前から親しくしている同級生がいたのだと教えてくれたが、これもよくある話というか女がよく使う手で、むしろこんな安易な手に引っかかる男はどんな間抜けだと思ったくらいだ。
若さの前では平穏など目の前の刺激にかき消される。彼女とはそれ以後会う事はなかったが、それさえも最近まで忘れていた。
なぜ今頃になって思い出すのだろう。
彼女といてつまらないわけじゃなかった。平凡な生活をしていた平凡な彼女との恋は使い慣れた毛布のように穏やかな暖かさに満ちていた。
町の映画館で見た映画も、よく行ったチェーン店のカフェも平凡で面白みなんてものはないが、気負う事も見栄を張る必要も無く、力が抜けて素のままで寛げた。
それがいかに貴重なものか、今になってその価値がわかる。
俺はそんな日常に甘えて子供のようなわがままと傲慢さで彼女を失った。大切にすれば良かったと後悔してももう遅い。こぼれた水は元の器に戻ることはないのだ。
いや、どちらにしろ別れはいつかやって来ただろう。これで良かったのだと思いたい。
俺は暗殺者だ。
もう「普通」であることは許されない。
「しょうがねえなあ。」
独りつぶやいた所に、携帯が鳴ってメローネからの連絡が入る。
「ターゲット追い込んだぜ。後はよろしくー。」
「了解。サクッと終わらせる。」
「あ、目玉忘れんなよ。」
「わかってるって。」
ターゲットの足音が近づく。
「さて、いきますか。」
路地に差すわずかな明かりを受けてナイフが光った。
完