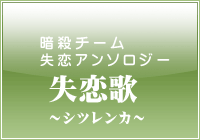子供にはまだ、早すぎる味だったかもしれねぇなァ。
Etude by ヤミ
ガキん時の初恋なんざ、大抵ありがちなパターンなんだよ。近所の幼馴染とか、花屋の看板娘とか、学校の非常勤講師とか。
非常勤講師。俺の初恋もそうだった。彼女は当時ハタチくらいだったんだろうか、本業は学生だって言っていた気がする。海外の有名な音楽大学に留学するための金が欲しいとかでさ、毎週火曜日と金曜日の午後に学校に来て俺たちに音楽を教えんのよ。栗色の髪を頭の後ろで一つにまとめてて、色白で、鈴が鳴るように笑うんだけど歌声はすんげー綺麗でさ。十歳やそこらの俺たちと変わらねぇくらいの身長で、なのにいつもペタンコの靴を履いているからちょっとはヒールの高い靴にしたらって言ったら、ヒールがあるとピアノを弾く時に踏ん張れないからって言ってた。
きっかけはなんだったんだろうな。たぶん初めて身近に“お姉さん”って存在が現れて、ただそれだけで舞い上がってたんだろうな。だってよ、それまで周りの女っていったらクラスのマセた女子どもか、いっつもどぎつい色のワンピースを着てる年増の女教師くらいしか知らなかったからよ。そんなところに若くて綺麗なお姉さんだぜ?俺だけじゃない。学校中の男子生徒が浮かれていたんじゃあねぇの?
隣で話を聞いていたプロシュートがククッと笑う。「あー、分かるわそれ。手前だって十分にガキのくせしてよぉ、同じガキの女子にゃ目もくれずに、おっぱいの成長しきった女ばかり気になってさ。しかも相手も自分に気があるんだってめでたい妄想ばかりしてよぉ」
「全くその通りだ」同じように喉の奥でクツクツ笑いながら、ホルマジオは空になった自分のグラスに琥珀色の液体を追加する。
「酒なんて飲めるわけないのによ、自分はもう大人だって信じたくて親の酒をくすねてさ。キッチンの影に隠れてちびっと舐めたりしてよ」
飲み干せるわけがないのに、今と同じくらいに並々とグラスにつがれたそれ。恐る恐る舐めた酒は旨さなど感じられず、舌の先がピリピリ痺れ苦味が口内に広がった。軽い眩暈と頭痛。
俺の通ってた学校はさ、音楽室だけ建物が別になってるんだよ。楽器の音が外に漏れてもいいようにかな。メインの校舎から細い渡り廊下が伸びてて、その先の分厚い扉を開けるとそこが音楽室。黒板の半分は五線が引いてあって、教卓が隅っこに置いてある代わりに黒板の前にはどでかいピアノ。机と椅子は普通のなんだけど、壁中に小さな穴が開いてて、授業が退屈になるとその穴をぼーっと数えたりしてさ。まぁ、それまでのよぼよぼのおじいちゃん先生が引退してその講師が来るようになってからは、壁の穴なんかより彼女ばかり見てたけど。
で、大抵の教室がそうであるように、音楽室も南側は全部窓になってんの。座学の時はカーテンを開けてて、演奏や合唱になるとカーテンを引いて。このカーテンってすげぇのな。確かに分厚いなとは思ってたいけど、音楽室から一歩外に出るとほとんど音が聞こえねぇ。
ちょうどその頃から俺はいわゆる不良って奴らとつるむようになってきててよ。しかも年上の女と自分が釣り合ってるって思い込んでるそのめでたい頭で、同じように年上の不良どもとも釣り合えるって思い込んでて。それで自分が強いんだって証明したくてバカみたいに喧嘩ふっかけてよ、酒と同じだな。
で、その日もなんでもない事に文句つけて頭二つ分デカい上級生に殴り掛かって、倍の力でボコボコにされて、やべぇと思って逃げ込んだのが音楽室だったんだ。
教卓の下に潜り込んで、息をひそめたまま殴られた部分の痛みが引くのを待っていた。生徒はとっくに帰っている時間だけどよ、まだ陽は沈みきっていねぇ。慌てて飛び出して上級生に見つかるよりは真っ暗になるまでこうしていようって、俺は身体を丸めたままウトウトしてた。
20分は経ったかな。急に音楽室の扉が開いて、誰かが入ってくる気配がしたんだ。俺はびっくりして飛び起きたが、もしかしたら上級生かもしれねぇとそのまま教卓の下に隠れていた。足音はまっすぐにピアノの方へ向かう。椅子を引く音。ギィ、とピアノの蓋が持ち上げられる。そんで次に聴こえてきたのはよ、静かな、ピアノの音色だった。
金曜日だ。俺は今日が何曜日だったかを思い出した。あの非常勤講師が学校に来る曜日だ。そういえば、ここのピアノは古いけど上質なピアノだから弾いていて気持ちがいいとか言ってたっけ。授業も学校の事務も終わらせたあと、こうやって毎週一人で練習しているんだろうな。
夕日が沈みかけて教室が暗くなってきてもよ、俺はまだ教卓の下に隠れたままピアノの音色を聴いていた。彼女が弾くのはどれも知らない曲だったが授業の音楽鑑賞みたいに眠たくなることは無くて、むしろいつまででも聴いていたいと思えた。しばらくすると彼女が席を立った気配があったが、教室の明かりをつけるとまた練習が再開した。
殴られた場所の痛みは引いていた。代わりに長い間身体を丸めて座っていたから、背中と尻が痛みだしていたっけ。そもそも隠れる必要なんて無いんだろうがなんとなく外に出づらくて、俺はピアノの練習が終わるまでその姿勢のまま教卓の下に隠れ続けていた。
「お前のその辛抱強さはガキん時からだったんだな」
仕事でのホルマジオの得意分野は潜入だ。時期が来るまで同じ場所に何時間も潜み続けるとこも少なくはない。そのことを引き合いに出されて、ホルマジオはさぁなと笑う。
「あぁ、でも確かにそれからあの日まで、俺は毎週隠れ続けたな。あの音楽室の教卓の下に。彼女のピアノを聴きたくてよ。俺だけが知っているっつーのがさ、ガキの小さな恋心を優越感で満たすんだ。物音ひとつ立てず呼吸も限りなく静かに、気配を完璧に殺す術は、確かにあの教卓の下で身につけた」
「人生何が役に立つのか分かんねぇな」
「全くだ」
グラスの液体は半分ほどに減っていた。あの頃は苦くてまずくて飲み込むことすらできなかったのに、今ではこんなにも甘い。
「それで?お前が潜入を辞めたあの日ってのは?」
プロシュートが先を促す。
「あぁ。失恋さ。青くせぇガキの淡い初恋が散った日さ」
さっきも言ったけどよ、俺は毎週金曜日の放課後に音楽室に通うのが習慣になっていたんだ。誰も知らない彼女っつーか、“先生”じゃあない一面を知れるのが嬉しくてよ。それだけでガキの恋心はどんどん膨れ上がって舞い上がって突っ走った。
で、2か月くらい経ったっけかな。その日もまるで今からデートするんだって浮かれた気分で音楽室に行ってよ。教卓の下に隠れながら彼女が来るのを待っていたんだ。
いつもと同じ時間に音楽室の扉が開いて、彼女の足音が聞こえた。でもよ、その日はもう一つ足音があったんだ。心臓が飛び出るかと思ったぜ。ハイヒールみてぇなコツコツって音じゃあ無かったから一緒に入って来たのは男かもしれねぇ。なんでだ?俺だけが知っている彼女の姿を他の男が見るのか?しかも彼女が鍵盤に向かう姿を俺みたいに隠れるわけでもなく、堂々と眺めることが出来るんだ。
「お前も堂々と見せてくださいって言えば良かったんじゃあねぇの?」
「うるせーよ。あの時は隠れて聞く以外に考えられなかったんだよ」
とにかくよ、その男に俺のことが気づかれるかもしれねぇからさ、急にその状況が怖くなってきて、心臓がバクバクなりだして、俺は今まで以上に気配を消してじっと固まった。相手は誰だ?何のためにここに来た?もし見つかったらどうする?俺は少しでも情報が欲しくて二人の会話に聞き耳を立てた。
彼女の声は高くてそれなりに聞き取ることができたんだが、やはり相手は男だったみてぇで、声も低くてよく聴こえねぇ。でもよ、学費が、とか、援助を、とか聞こえてきたから、留学費用の話じゃねぇかってピンときた。海外留学にかかる金がどれだけ大金かってことくれぇは当時の俺でも知っていたし、彼女が他にも掛け持ちで仕事をしているってのも噂で聞いていたからな。
じゃあこの男は彼女の留学費用を援助してやるとでも言い出したのか?それって良い奴なんじゃあねぇのか?単純な俺はよ、ちょっとだけその男から警戒心を解いたんだ。
ホルマジオはグラスに残っていた最後の琥珀色をぐいと飲み干す。
夕暮れの音楽室。教卓の下に隠れた十代の自分。密かに恋心を抱いていた音楽講師。
そしてその日、耳に届いたのは聞きなれたピアノの音色ではなく、それを奏でる筈だった彼女の、押し殺したような嬌声と泣き声だった。
金に困って自分を売るなんて今となっちゃ珍しくもなんともねぇ話なんだけど、流石にあの時は絶望を感じたぜ。つってもその時はその行為と金が結びつかなくて、ただただ惚れた男に身体を開いているんだって思っていたけどな。まぁどっちにしろガキには衝撃がでか過ぎた。心臓は破裂するんじゃないかってくらいにバクバク鳴って足はガクガク震えて、目の前は真っ暗だ。それなのに聴覚だけは鋭くなって、聞きたくもない音をひとつひとつ丁寧に拾いやがる。机の軋む音。何かを打ち付けるような音。それに合わせて漏れる水音に、男の笑い声。彼女の口からは泣き声が消えて、嬌声だけが零れていた。
「…そりゃヒデー失恋だな」
プロシュートがその整った眉をしかめながら言う。だが、当のホルマジオは至って明るい口調だ。
「だろ?ついでによ、その時間があんまりにも長いんで、ちょっとずつ冷静さを取り戻した俺は教卓の下から顔だけ出して覗き見してみたんだよ。そしたらよ、男の後ろ姿と、こっちに尻を突き出して机にうつ伏せになってる彼女の細い足が見えたんだ。背が低いから必死に爪先立ちになって、いつも履いているペタンコの靴の裏が小さく震えていた」
そこまで聞いてプロシュートは何か思い当たったようで、グラスに伸びかけていた手を止めホルマジオの方を向く。
「だからか?ヒールの無い靴を履く女は嫌いだっていうお前の変な好みは」
「あぁ、そうだ。そーいやそもそも女の好みの話をしてたのに、まさかガキん時の失恋話まで曝しちまうとは」
「お前が勝手に話し出したんだろうが。清楚な女が好みだが靴だけはヒールでないとダメだ、って」
「そうなんだけどよ。この酒を飲んでいたら思い出したんだ」
空になったグラスを手のひらに持て余しながらホルマジオは続ける。
「トラウマになっちまったんだよな。あの時の光景が。いや、立ちバックは好きだぜ?あの無理やり感がたまんねぇ」
「聞いてねーよ」
すかさずプロシュートが口をはさむ。それをハハ、と軽く受け流して、グラスに新しく取り出した酒を注ぐ。
結局あの後、彼女がどうなったかは知らない。毎週金曜日に音楽室に行くことも無くなった。一度だけ渡り廊下まで歩いたことがあったが、分厚いカーテンのせいでピアノの音色もそれ以外の音も聞こえてくることは無かった。次の春には留学費用が溜まったからと、非常勤講師のバイトを辞めて海外に行ってしまった。
ホルマジオは新しく注いだ酒を飲み干す。先ほどまでのよりも苦味の強い、だが後味のさっぱりした酒だ。歳を重ねるたびに旨いと思える酒が増えていく。でもきっと、いつまで経ってもヒールの無い靴を履く女だけは苦手なんだろうなと、ぼんやりと考えながら空になったグラスに新しい一杯を注いだ。
完